C05では、電子がターゲットに衝突して制動放射線を放つ仕組みを、クラマースやクーレンカンプの理論を通して見てきました。
あのとき扱ったのは、放射されるX線の「量」や「エネルギー分布」を説明するための、いわば“平均的な”モデルでしたね。
ところが、電子はただ減速するだけではありません。
どの方向に曲がるか、どの角度で放射するか――その違いが、放たれる光の表情を大きく変えます。
そこで登場するのが、ゾンマフェルトの理論式です。
この式は、電子が放射するX線(制動放射線)の角度角度分布を表すもので、制動放射線のスペクトルをより立体的に理解する鍵になります。
今回はそのゾンマフェルトの理論式を手がかりに、「光が放たれる方向」まで踏み込んで見ていきましょう。
制動放射線スペクトルをもう一度見直そう
制動放射線の話をもう少し掘り下げる前に、まずはC05で扱ったクラマース式を思い出しておきましょう。
制動放射線のスペクトルは“おおよそこういう形をしている”というイメージをつかんでおくことで、次に登場するゾンマフェルトの理論式の意味がぐっと見えやすくなります。
クラマース式のおさらい
制動放射線は、電子が金属ターゲットに突入して急減速するときに放たれる電磁波(X線)のことでしたね。
C05では、そのエネルギー分布――つまりどんな波長(エネルギー)の光子が、どのくらいの強度(量)で放射されるか――を、クラマース式で表現しました。
クラマース式は、古典電磁気学を基礎として導かれた近似式です。
電子の運動エネルギー E0 と放出されるX線のエネルギー E の関係を考え、強度 I(E) が E0-E に比例するという単純な形をしています。
その結果、エネルギーが高くなるほどX線の強度は減少し、低エネルギー側に向かってなだらかに増加するスペクトルが得られます。

忘れがちじゃが強度っちゅうのは、光子の“力”と“数”の掛け算じゃ。
つまり総エネルギーのことじゃな。

図で表すとこういった感じになるよ。

この式は実験結果をよく再現し、制動放射線の“平均的な姿”をつかむには非常に有用です。
しかし、クラマース式の中では放射がすべての方向に一様に起こると仮定されています。
つまり、どこから観測しても同じ強度で光が出ているという、やや単純化された世界の話なのです。
角度が無視できない理由
実際の電子は、進行方向をもって運動しています。
そして放射されるX線は、その運動方向に応じて特定の角度分布をもっています。
電子がどの方向に向かってブレーキを踏むか――その違いが放射の強さを左右するのです。
電子がターゲット原子核の近くを通過するとき、その軌道がわずかに曲がります。
この曲がり方は入射角や位置によって変化し、それが光の放射方向に反映されます。
つまり、観測する角度によってスペクトルの形自体が変わってしまうのです。
クラマース式ではこの角度依存を考慮していないため、厳密には現実の放射スペクトルを完全に説明できません。
そこで登場するのがゾンマフェルトの理論式です。
この式では、放射強度を角度とエネルギーの両方の関数として扱い、電子の運動方向との関係を明確に示すことができます。
次の章では、このゾンマフェルトの理論式がどのような考え方に基づいているのかを見ていきましょう。
ゾンマフェルトの理論式とは
クラマース式では、制動放射線がどんなエネルギー分布を示すかを説明できましたが、角度の要素は含んでいませんでした。
現実の放射現象をより正確に表すためには、電子の運動方向と放射の向きの関係――つまり角度依存性を考慮する必要があります。
ゾンマフェルトの理論式は、制動放射線の放射角度分布に応える形で登場しました。
理論が生まれた背景
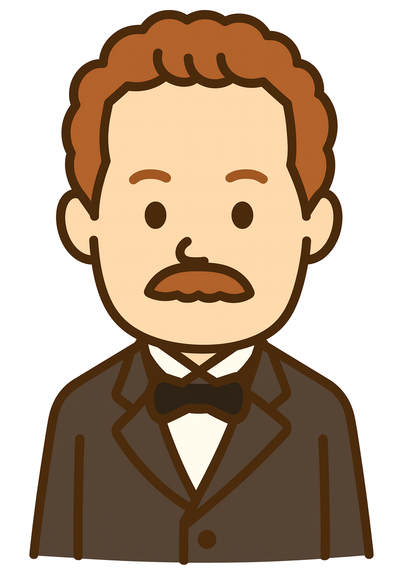
1920年代、ゾンマフェルト(A. Sommerfeld)は電子が相対論的な速度で運動するとき、古典的な理論では精度が足りないことに気づきました。
電子が光速に近づくほど、ローレンツ因子 γ によってその運動エネルギーが大きくなり、放射のされ方も変化します。
また、電子と原子核との間の相互作用は単なる「電荷のやり取り」ではなく、量子論的な確率のゆらぎを伴う現象です。
ゾンマフェルトは、これらの点を踏まえクラマース式を拡張し、角度分布をもつ放射強度の式を導きました。
この理論式は、電子の速度・放射角度・エネルギーをすべて含む形で表されており、「電子がどの方向にどの程度のX線を放つか」を数学的に記述するものです。
要するに、ゾンマフェルトの理論式は、古典理論の「均一放射」という前提を壊し、放射の向きによって強度が異なるという現実的なモデルを与えたわけです。
理論式の形と意味
ゾンマフェルトの理論式では、放射強度 I(θ,E)が電子の速度 v、角度 θ、および放出される光子のエネルギー E に依存して表されます。
具体的な式は複雑なので割愛しますが、本質は「どの角度方向にどれくらいエネルギーが放たれるか」を示すことにあります。
特徴的なのは、電子エネルギーが低い場合(keV領域)では放射は横方向に広がり、電子エネルギーが高くなる(MeV領域)につれて、放射が電子の進行方向(前方)に集中するという点です。
keV領域では電子の速度はそれほど速くないため、相対論的な効果はほとんど現れず、放射はほぼ全方向に近い分布を示します。
一方、電子の速度が光速に近づくMeV領域では、相対論的効果が顕著となり、放射は前方に強く集中します。
つまり、電子が速くなるほど放射角度は狭まり、後方や側方にはほとんど放射されなくなります。
この前方指向性こそが、ゾンマフェルトの理論式が示す重要な特徴であり、角度分布を考慮しないクラマース式との大きな違いです。
また、この理論式は相対論的補正を含むため、高エネルギー電子による制動放射をより正確に扱うことができます。
そのため、X線管の設計やスペクトル解析においても、ゾンマフェルトの理論式は重要な参照モデルとして位置づけられています。
制動放射線の向きとエネルギーの関係
制動放射線は、電子が原子核の近くを通るときに急減速され、その運動エネルギーの一部がX線として放出される現象です。
このとき、「どの方向に放射されるか」は電子の持つエネルギー(=速度)によって大きく変わります。
つまり、電子のエネルギーが高いほど“進行方向に集中し”、低いほど“あちこちに広がる”という特徴があるんです。
エネルギーが高いと前方に放射される

電子のエネルギーが高く、たとえば数MeVといった領域では、電子は光速に近い速度で運動しています。
そのため、電子が急減速するときに発生する電磁波(=制動放射線)は、電子が進んでいた方向(0°方向)へと強く放射されます。
この現象を「前方放射」と呼びます。
これは、相対論的な効果によるものです。
高速で運動する電子のまわりでは、時間や空間の見え方が変化し、電磁波の放射分布も電子の進行方向に“押しつぶされる”ように集中します。
その結果、高エネルギーの電子ほど、X線は電子の飛んだ方向へ向かって放たれるのです。
この現象は放射線治療に用いられる直線加速器(リニアック・ライナック)で見られる制動放射です。
白い三角形のターゲットに向かって上から下に電子が入射しています。
発生する制動放射線も下方向に分布しているのが分かるかと思います。
つまり、0°方向に発生しています。
エネルギーが低いと横方向に広がる

一方で、電子のエネルギーが低く、数十keV程度のときには話が変わります。
この場合、電子の速度はそれほど速くないため、相対論的な影響はほとんど無視できます。
そのため、放射されるX線は進行方向だけでなく、ほぼ全方向に放出されます。
実験的には、特に±90°方向(電子の進行方向に対して横向き)に強い放射が見られます。
この現象は、一般撮影やCTで見られる制動放射です。
ターゲットに向かって、左から右に電子が入射しています。
発生する制動放射線は下方向に分布しているのが分かるかと思います。
つまり、90°方向に発生しています。

低エネルギー電子では「横に広がる放射」
高エネルギー電子では「前に集中する放射」
となるわけです。
ゾンマフェルトの理論式が示したこと
これまで見てきたように、制動放射線の放射方向は電子のエネルギーによって大きく変わります。
では、なぜそんな違いが生じるのでしょうか?
そのヒントを与えてくれるのが「ゾンマフェルトの理論式」です。
この式は、電子がターゲット原子の近くを通るときに生じる電磁波(=制動放射)の放射角度分布を理論的に説明するものです。
理論が教えてくれる“放射の方向性”
ゾンマフェルトの理論式では、電子がどの角度方向にどれだけの強さで電磁波を放つかが定量的に表されます。
式そのものは複雑ですが、要点は次のようにまとめられます。
- 電子の速度が遅いとき(keV領域) → 放射はほぼ全方向に近い分布を示す
- 電子の速度が速いとき(MeV領域) → 放射は電子の進行方向に集中する
つまり、エネルギーが高いほど放射角度は狭まり、電子の進行方向へと「押しつぶされる」ように放射が集まっていくわけです。
これは相対論的効果(電子の運動が光速に近づくこと)によって、電磁場の変化が前方に集中して見えるためです。
このようにゾンマフェルトの理論式は、電子のエネルギーによって放射の角度分布が変化することを定量的に裏づける理論といえます。
さっきから「理論式」や言うてるのに、
式自体は紹介しないんか?


式自体は出題されないからね。
覚えなくても良いって意味で紹介しないよ。
その割り切りが好きやねん!

スペクトル形状への影響
制動放射線スペクトルとは、放射されたX線のエネルギー分布を示したグラフのことです。
もし放射が全方向に均一であれば、観測されるスペクトルは比較的なだらかな形になります。
しかし実際には、観測する角度によってスペクトルの形が変わるのです。
たとえば、電子の進行方向に対して前方側(0°付近)を観測すると、高エネルギー成分が強く現れます。
逆に、横方向(90°付近)では低エネルギー成分が優勢になります。
これは、前方放射では高エネルギーの光子が多く放たれ、横方向では比較的エネルギーの低い光子が放たれるためです。
ゾンマフェルトの理論式によると、
角度ごとの放射強度 I(θ,E)を積分してスペクトルを求めると、
高エネルギー電子では“前方に鋭いピーク”が現れ、低エネルギー電子では“広くなだらかな分布”となります。
要するに、角度分布を無視したクラマース式では見えなかった「方向によるスペクトルの差」が、
ゾンマフェルトの理論式によって初めて説明できるようになったということです。
この考え方は、医療で使われるX線の設計にも深く関わっています。
次の章では、放射の方向性が実際のX線管の構造や利用方向にどう反映されているかを見ていきましょう。
このへん、難しくないですか?

せや。目ぇ回るで・・・


このあたりは難しいからのぅ。
分からなければ、読み飛ばすのも手じゃぞ。

そうだね。
高エネルギーのものは前方に。
低エネルギーのものは側方に。
ってくらいの認識でもいいね。
医療現場でのイメージ
ここまで見てきた放射方向の違いは、単なる理論の話ではありません。
実はこの性質が、医療で使われるX線管の構造設計そのものに関わっています。
どの方向に強くX線が出るのかを理解しておくと、装置の向きや照射野の形にも納得がいくようになります。
X線管での放射方向と利用範囲
X線管の中では、電子が陰極(フィラメント)から陽極(ターゲット)へと加速され、そのターゲットで制動放射線が発生します。
このとき、電子のエネルギーは通常およそ数十〜百keVほど。
つまり、ゾンマフェルト理論でいうところの「低エネルギー領域」にあたります。
そのため、放射されるX線は電子の進行方向に集中せず、ターゲット面のほぼ垂直方向(90°付近)へ多く放たれます。
だからこそ、医療用X線管はターゲットを傾けた「斜入射構造」になっており、
この側方に放たれる放射線を下向きに取り出して利用しているのです。
この仕組みを使うことで、装置全体をコンパクトにしつつ、均一な照射野を得られるよう工夫されています。
つまり、ゾンマフェルトの理論式が示した“横方向優勢”の特性を、X線管の設計が実際に活かしているということです。
へぇ。意外と考えられとるんやなぁ。

制動放射線のエネルギー
制動放射線のエネルギーは入射電子と原子核の位置関係が大きく関わっています。
近くを通るか、遠くを通るか

電子が原子核のそばを通る場合(図の左)、電子にはクーロン引力が強く働きます。
そのため、電子は多くの運動エネルギーを失うことになります。
その結果として、発生する制動放射線のエネルギーは大きくなります。
電子が原子核の遠くを通る場合(図の右)、電子にはクーロン引力は少ししか働きません。
そのため、電子は運動エネルギーをあまり失わずに済みます。
その結果として、発生する制動放射線のエネルギーは小さくなります。
実際の過去問を見てみよう。
ちょっと(かなり?)古いですが、2001年に実施された第53回国家試験からのご紹介。
少し改編していますが、ご参考までに。
第53回 2001年 問14(改)
制動放射線で正しいのはどれか。2つ選べ。
- 診断用X線領域では制動放射線が主である。
- 診断領域での発生効率は10%程度である。
- 総エネルギー(全強度)は管電圧の2乗に反比例する。
- 強度はターゲット物質の原子番号に反比例する。
- 放射方向の角度分布は入射電子のエネルギーによって変化する。
答えを確認する。
正解は 1 と 5 です。
できましたか?簡単な解説を置いておきます。
- ① 診断用X線領域では制動放射線が主である。〔正〕
診断領域(数十~百 keV)では、連続スペクトルの制動放射線が主体です。特性X線は一部に重なる程度です。 - ② 診断領域での発生効率は10%程度である。〔誤〕
診断用X線管の効率は1%未満で、その他はほとんどは熱になります。放射線治療エネルギー帯なら10%に近くなります。 - ③ 総エネルギー(全強度)は管電圧の2乗に反比例する。〔誤〕
全強度は管電圧の2乗に比例します(反比例ではありません)。おおまかに $I∝ZV^2$ の関係です。 - ④ 強度はターゲット物質の原子番号に反比例する。〔誤〕
強度は原子番号 Z に比例します。Z が大きい(例:W)ほど制動放射線は出やすくなります。 - ⑤ 放射方向の角度分布は入射電子のエネルギーによって変化する。〔正〕
MeV帯では前方に集中、keV帯では横方向(90°付近)に広がります。ゾンマフェルトの理論式で裏づけられます。このC06の記事でご紹介した通りです。

ゾンマフェルトが出題される機会は多くはありませんが、知っていると色々と理解が深まりますよ。
発生効率や強度に関しては次のC07で触れています。
医療現場でのかかわり
ゾンマフェルトの理論で示された“放射の方向性”は、実際の医療装置でもそのまま活かされています。
ここでは難しい話は抜きにして、現場でどう使われているかだけを整理しましょう。
X線管での放射方向と利用範囲
診断用X線装置では、電子のエネルギーは数十〜百keV。
つまり、横方向(90°方向)のX線強度が高くなる領域です。
そのため、X線管はターゲットを斜めに傾け、横に出る放射線を下向きに取り出す構造になっています。
私たちが普段使っている一般撮影装置は、まさにこの“横方向放射”を利用しています。
一方、放射線治療装置(リニアック)の場合は電子エネルギーが数MeVと高く、ゾンマフェルト理論でいう前方放射(0°方向)のX線強度が高くなる領域に入ります。
したがって、リニアックでは電子の進行方向そのままに放射線を取り出し、治療ビームとして利用しています。
まとめ
この記事では、制動放射線の放射方向が電子エネルギーによって変化するという点を整理しました。
振り返って、ポイントを簡潔にまとめておきましょう。
- 制動放射線の放射方向は、電子のエネルギーによって大きく変わる。
- 診断領域(keV帯)では、放射は電子の進行方向に対してほぼ90°(横方向)が強い。
- 治療領域(MeV帯)では、放射は電子の進行方向(前方・0°方向)に集中する。
- ゾンマフェルトの理論式は、この放射の方向性(角度分布)を理論的に裏づけたものである。
- この性質は、一般撮影用X線管やリニアックの装置設計にもそのまま反映されている。

エネルギーが変われば、放射の向きも変わる。
それを式で説明したのがゾンマフェルト理論。
無理に式を覚えなくても、「ああ、理屈はこういうことか」と納得できていれば十分ですよ。
お願い
本サイトに掲載されている図やイラストの著作権は管理人にあります。
無断掲載や転載はお断りさせていただきます。
また、リンクフリーではありますが、画像などへの直リンクはお控えください。
次に読むならコレ!電爺的おすすめ内部リンク

ほれ、ここまで読んだんなら、次はこのあたりを見ておくとえぇぞい。
次に読むならコレ!たまのすけおすすめ外部リンク

このあたりも参考になるかもしれません。
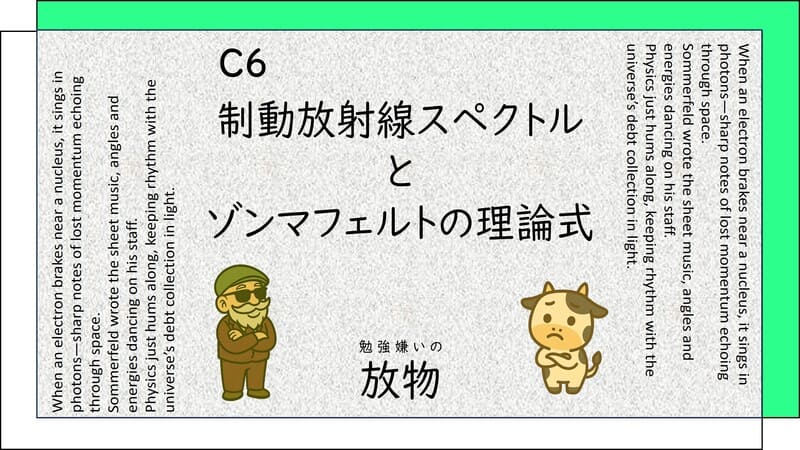
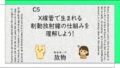
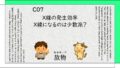
コメント