ご存知の通り、原子核の中には陽子と中性子がギュッと詰まっています。
その中の陽子はすべて同じ正の電荷を持っています。
普通ならクーロン力で反発しあってバラバラになりそうなのに、なぜ原子核は崩れないのでしょうか?
この記事では、原子核をまとめる「核力」の正体と、その特徴のひとつである「荷電独立性」についてわかりやすく解説します。
陽子同士、陽子と中性子、中性子同士 ― どんな組み合わせでも同じように働く核力。
その性質を図や実際の試験問題を交えて整理していきます。
核力には「強い力」という特別な役割があり、電荷に関係なく核子を結びつける仕組みがあります。
この性質を理解することで、原子核が安定する理由や試験で問われるポイントがスッキリと見えてきます。
核力とは?
原子核の中では、陽子と中性子が非常に強く結びついています。
その結びつきを生み出しているのが「核力」と呼ばれる力です。
4つの力の中の「強い力」
私たちの世界に働く力は、大きく4種類に分けられます。
- 重力
- 電磁気力(クーロン力など)
- 強い力(核力)
- 弱い力
このうち「核力」は、陽子や中性子などの核子どうしを結びつける特別な力です。
「4つの力」を覚えていますか?
忘れてしまった方は4つの力:強い力・弱い力・電磁気力・重力って何?自然界の4つの力まとめで復習を。

原子核の中の話ですから、関係するのは「陽子」と「中性子」ですね。
ときどき軌道電子が原子核の中にあると思い込んでいる方を見かけますが、軌道電子はたまたま原子核の中に存在するタイミングはあっても、常駐している訳ではありませんのでご注意を。
核子(陽子・中性子)の組み合わせは3通り
核子は、電荷をもつ「陽子」と、電荷をもたない「中性子」の2種類があります。
それぞれの組み合わせは次の3通り:
- 陽子どうし
- 陽子と中性子
- 中性子どうし
そして驚くことに、どの組み合わせでも核力はほぼ同じ強さで働くのです。これが後で学ぶ「荷電独立性」につながっていきます。
陽子と中性子の組み合わせを見てみよう
核子には陽子と中性子があり、組み合わせは3通り考えられます。
ここでは、それぞれの場合に働く力を整理してみましょう。
陽子と陽子の組み合わせ

陽子同士の結合の場合、お互いに引き合う「核力」(図中の白矢印)のほかに離れあおうとする電磁気力の一種である「クーロン斥力」(図中の黒玉矢印)が働きます。
それでも原子核の中でバラバラにならないのは、核力がクーロン斥力を上回るほど強く働くからです。
陽子と中性子の組み合わせ

片方は電荷をもち、もう片方は電荷をもたない組み合わせです。
このときはクーロン力の影響はなく、純粋に核力だけが2つを結びつける役割を果たします。
つまり、陽子と中性子の結合の場合は「核力」のみが働きます。
中性子と中性子の組み合わせ

中性子は電荷をもたないため、クーロン力は働きません。
しかし核力はしっかり作用し、中性子どうしでも強く引き寄せ合うことができます。
つまり、中性子同士の結合の場合も「核力」のみが働きます。
荷電独立性とは?
核子間には、どんな組み合わせでも結合するために核力が働いていました。
次はその核力の大きさを見ていきましょう。
どの組み合わせでも核力の強さは同じ
陽子どうし、陽子と中性子、中性子どうし――。
電荷の有無や組み合わせが違っても、核力の強さはほぼ同じです。
この「電荷に依存しない性質」を 荷電独立性(charge independence) と呼びます。
つまり核力は「陽子だから強い/中性子だから弱い」といった区別をせず、平等に働いているのです。
クーロン力とのちがいに注意
ここで混同しやすいのがクーロン力です。
クーロン力は電荷が同じなら反発し、異なれば引き合うというように、電荷に依存して変化する力です。
一方で核力は、電荷を気にせず核子を結びつける力。
この違いをしっかりと整理しておけば、試験問題でも迷わうことも少なくなります。

クーロン力は電荷に依存するけど、核力は電荷に依存せずに独立しているんだよ。
核力の有効範囲
核力はとても強い力ですが、どこまでも働くわけではありません。
この力がどのくらいの距離まで有効なのかを見ていきましょう。
有効範囲内では、少し離れた距離で最も強く働く
核力は「強い力」と呼ばれますが、距離が近いほど強くなるわけではありません。
核子どうしが近づきすぎると、核力はあまり強く働かず、少し距離が離れたところで、引力として最も強く作用します。
このような性質が現れるのは、核力の有効範囲が約1 fm(フェムトメートル)と非常に短い距離に限られているためです。
この点は、距離が近いほど強くなるクーロン力や重力とは、性質が大きく異なる部分です。
つまり、核力は有効範囲内であれば、「離れるほど強くなる距離領域」をもつ力だと考えることができます。
有効範囲を超えると「ゼロ」になる

核力には有効範囲があります。
その特徴も少し変わっています。
クーロン力であれば、近ければ強く、離れれば弱くなります。
X線の線量も同様です。
距離の逆二乗則でしたね。
核力の場合は、大げさな図で示したように、近いとそんなに強く働きません。
遠いほうが強く働きます。
この時点でクーロン力などとは逆の性質を持っています。
さらに、核力には有効範囲が設定されています。
有効範囲を超えてしまうと、途端に「0」になってしまいます。
つまり、「核力は有効範囲内では離れるほど強くなり、有効範囲を超えるとゼロになる。」という特徴があります。
このように核力が核子をまとめると、その結合のエネルギーが質量の減少として現れます。
これを質量欠損と呼ばれ、核力の存在を裏づける大切な現象でしたね。
(詳しくはA15:原子核の質量が軽くなる?質量欠損とエネルギーの記事で解説しています)
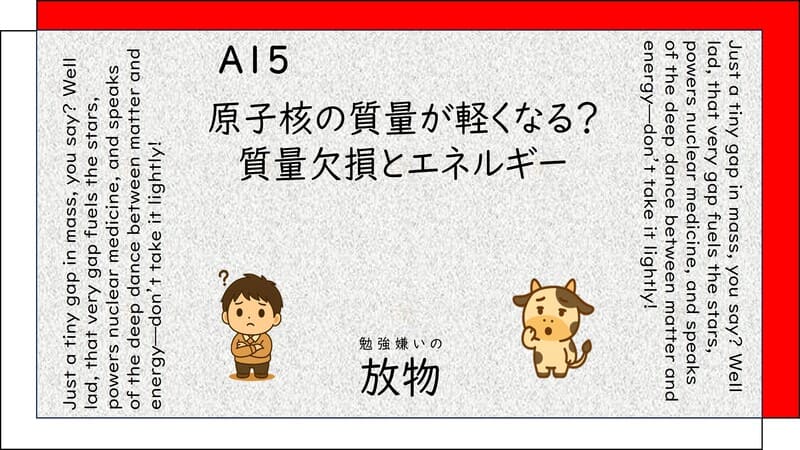
核力はどう生まれる?中間子と交換力の話
さらに、核力にはもう一つ重要な視点があります。
それは、核子同士が 中間子 をやり取りすることで結びつく、という仕組みです。
この「中間子の交換」によって力が生じるため、核力は交換力と呼ばれることがあります。
より深いレベルでは、中間子の内部に含まれる グルーオン という粒子が、核子どうしの結びつきを媒介しています。
このような核力の成り立ちを最初に理論的に示したのが 湯川秀樹博士 で、博士はこの研究により日本人として初めてノーベル物理学賞を受賞しました。
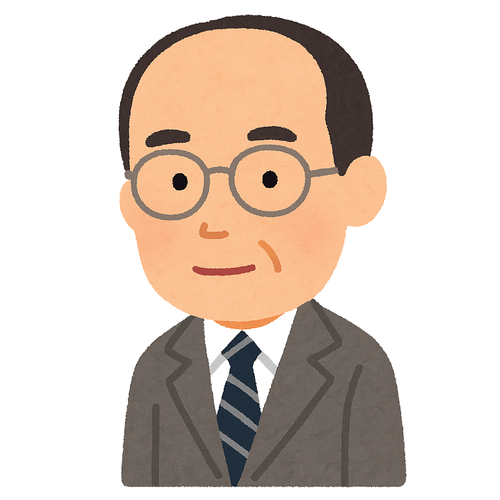
実際の問題を見ていきましょう。
ちょっと古い問題ですが、いかがでしょうか?
第57回 2005年 PM41
核力について誤っているのはどれか。
- 陽子を中性子に変える。
- 中性子間でも働く力である。
- 電子の質量欠損と関連がある。
- クーロン力と同じ性質の力である。
- 核子の種類にかかわらす荷電独立性がある。
解答を確認する。
答えは 4 です。
クーロン力とは異なる性質の力でしたね。
有効範囲の有無などを考えてもらうと、違う性質であることが分かるかと思います。
また、クーロン力は電荷に依存し、核力は電荷に依存せず独立していましたね。
医療現場でこの知識がどう役立つの?
現場では関係ないと思いきや、核力や荷電独立性の性質は、放射線治療の分野に関係があります。
たとえば 陽子線治療や重粒子線治療 では、原子核の中に閉じ込められた陽子や中性子を取り出して高速で飛ばし、がん細胞を狙って照射します。
このとき核子が安定して存在できるのは、まさに 核力が陽子・中性子を強く結びつけているから です。
また、荷電独立性によって陽子や中性子が区別なくまとまるため、原子核は安定し、その安定性を利用して高エネルギーの粒子線を医療に応用することができます。
つまり、核力の性質を理解することは、「なぜ粒子線治療が成り立つのか」 を物理学的に裏づけることにもつながるのです。
直接的に核力や荷電独立性を意識して仕事をすることはありませんけどね。
まとめ
核力は、陽子や中性子を原子核の中で結びつける、とても重要な力です。
電荷の有無に関係なく同じ強さで働くという性質を 荷電独立性 といい、この性質によって、原子核は安定して存在することができます。
また、核力はどこまでも働く力ではなく、有効範囲は約1 fmと非常に短いのが特徴です。
有効範囲内では、少し離れた距離で強く働きますが、範囲を超えると急激に弱まり、ほとんど作用しなくなります。
クーロン力との違いを意識して整理しておくことが、核力を正しく理解するためのポイントです。

核力って、原子核を形づくるための“見えないのり”みたいなものなんだ。
荷電独立性までしっかり理解しておけば、国家試験でも安心だよ。
お願い
本サイトに掲載されている図やイラストの著作権は管理人にあります。
無断掲載や転載はお断りさせていただきます。
また、リンクフリーではありますが、画像などへの直リンクはお控えください。
次に読むならコレ!電爺的おすすめ内部リンク

ほれ、ここまで読んだんなら、次はこのあたりを見ておくとえぇぞい。
もっと知りたい方へ!たまのすけおすすめ外部リンク

ここまで読んできた皆さんなら、もう一歩踏み込んだ知識に触れてみたくなるはずです。そんな方におすすめの外部リンクを紹介します。
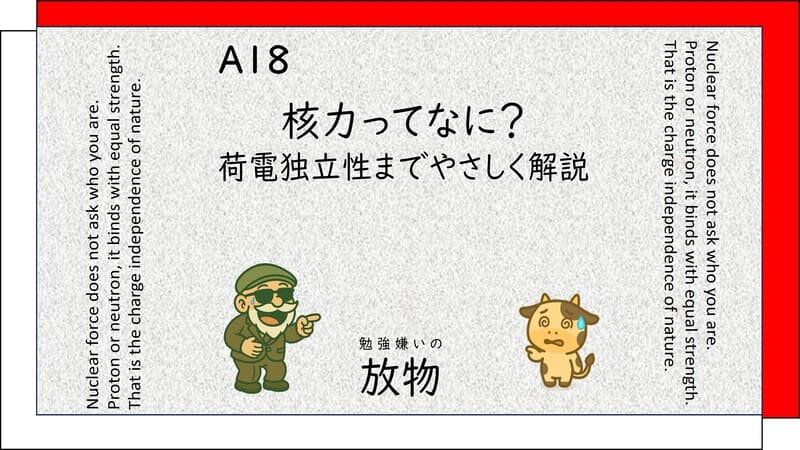
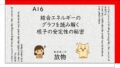
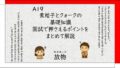
コメント