「この物質に含まれる電子って、いったい何個あるの?」
放射線やX線の挙動を学ぶうえで、「電子の数」が重要になる場面はたくさんあります。
ですが、実際に数を数えるわけにもいかず、どうやって求めればいいのか困ってしまう人も多いのではないでしょうか。
この記事では、「電子の数」を式で求める方法を解説していきます。
その過程で「原子の数」も求められるようになります。
電子の数を出すには、密度・体積・原子量・アボガドロ数などの情報をもとに、いくつかの手順を踏んで計算します。
式の立て方がわかれば、問題ごとに応用することもできるようになりますよ。
放射線技師国家試験でも頻出の「電子数の計算」ですが、公式を暗記するだけではなかなか身につきません。
この記事では、計算の意味から丁寧に整理していくので、しっかり理解して使いこなせるようになります。
それでは見ていきましょう。
まずは文字と物理量を確認しよう
使う文字が何を示しているか分からないと、始まりませんからね。
ここの部分、疎かにする人が結構いるんですが、放置しちゃダメなところです。
まずは文字の定義から
ここで登場する文字を一気に定義付けしていきましょう。
文字は一般的に使われているものにしておきましょう。
- NA:アボガドロ数 [1/mol]
- ρ:物質の密度 [g/cm3]
- V:物質の体積 [cm3]
- A:質量数
- Z:原子番号
馴染みのない方の為にちょっと用語の解説を挟んでおきましょう。
アボガドロ数
単位をよく見て下さい。
アボガドロ数の単位は [1/mol] です。1の部分を個にして [個/mol] としても良いです。
(単位の世界で「1」は「個数」や「回数」を表すときに使われます。)
これは、「物質が1mol集まったら、そこには何個の原子がありますよ」ということを示しています。
数字で表すと、6.02×1023個です。
つまり、物質が1molあると、その物質の中に原子が6.02×1023個入っているということになります。
物質の密度
こちらも単位をよく見て下さい。
密度の単位は [g/cm3] です。
これは1cm3の体積あたりの質量を示しています。
SI基本単位で示すと[kg/m3]となりますが、常用されるのは[g/cm3]です。
要は、どれだけギュッと詰まっているかを示しています。
当然、密度が高ければギュッと詰まっていて、密度が低ければスカスカということになります。
見かけ以上に重たいなってものは高密度です。鉛なんかが良い例ですね。
反対に大きくても軽い発泡スチロールは低密度と言えますね。
物質の体積

物質(物体)の大きさを示したものですね。
単位をみると、 [m3] となっています。
これは [m] 3つを掛け算してねという意味でしたよね。
つまり、「長さ」×「長さ」×「長さ」でOKですね。
サイコロ状の物体であれば、「縦」×「横」×「高さ」ですね。
質量数と原子番号

説明の必要はないかもしれませんが、念のため。
質量数は原子核の中にある核子の総数です。
簡単に言うと、「陽子」と「中性子」の合計数です。
それに対して原子番号は「陽子」の数です。
これも復習ですが・・・
原子1個に含まれる陽子の数は 原子番号Z で表します。
したがって、原子1個に含まれる電子の数も 原子番号Z で表します。
「原子数」や「電子数」はどうやって求めるの?
原子数を求めてから、電子数を求めることになります。
焦りは禁物です。順を追って見ていきましょう。
まずは質量を確認しよう。
問題文中に質量が明記されていれば問題ありません。
その数字や文字を使ってください。
だいたい「m」が充てられることが多い印象です。
問題は明記のない場合です。
質量の明記がない場合は、何とかして質量を表現しなくてはなりません。
ここでも単位が役に立ちます。
質量の単位は [kg] ですが、原子のような小さいものの場合は [g] で良いでしょう。
先ほど定義した文字の中から、単位をよく見て組み合わせれば、質量が表現できそうではないですか?
えっ?できない?
2文字組み合わせると・・・
密度と体積の単位を組み合わせて見て下さい。
ρ[g/cm3] と V[cm3] です。
掛け算してみると、 [g] になりますよね。
質量は密度と体積の積で表すことができます。
文字で表すとこうなりますね。
$$
\color{#B22222}{
m=ρV
}$$
続いて mol 数を求める(密度・体積・原子量)
厳密にいえば「モル質量」ということになりますが、放物では「モル数」で差支えないでしょう。
また、本来は「原子量」に当たる部分も「質量数」で考えて差し支えありません。
放物でだけですよ。
従いまして、物質に含まれるモル数は「質量」mを「質量数」Aで除せば求められます。
質量が定義・明記されていない場合は、密度と体積を駆使して表現します。
$$
\color{#B22222}{
\pmb{
\begin{aligned}
モル数&=\frac{質量m}{質量数A}\\[12pt]
&=\frac{密度ρ\cdot体積V}{質量数A}
\end{aligned}}}
$$
こちらの知恵袋も参考になります。
是非ご一読ください。
アボガドロ定数で「個数」に変換する
原子数はモル数とアボガドロ数の積で表現することができます。
モル数は物質の中に何mol入っているか。
アボガドロ数は1molあたりに原子がいくつ入っているかを示していましたね。
したがって、この2つを掛け合わせることによって、物資中に含まれる原子の数を表すことができるようになります。
$$
\color{#B22222}{
\pmb{
\begin{aligned}
\text{物質に含まれる原子数}&=\text{モル数}\cdot\text{アボガドロ数}\\[12pt]
&=\frac{\text{密度}ρ\cdot\text{体積}V}{\text{質量数}A}\cdot N_A\\[12pt]
&=\frac{ρ\cdot V}{A}\cdot N_A\\
\end{aligned}}}
$$
電子数は「原子数 × Z」で出せる!


原子の構造を思い出してください。
原子の中心には原子核があり、その中に陽子が入っています。
原子核の周りを軌道電子が周回しています。
電気的に偏りのない中性原子においては、陽子と軌道電子の数は等しいんでしたよね?
(特にイオン化しているなどの断りがない限りは中性原子として扱います。)
詳しくはA11:原子と原子核のちがいをやさしく解説|構造・役割・力の関係がわかる!もご参照ください。

ひとつの原子の中で陽子数を表すものがありましたね?
覚えてますか?
そう、原子番号Zでしたね。
つまり、1つの原子に含まれている陽子数は軌道電子の数と等しく、それは原子番号で表すことができます。
物質に含まれる陽子数と電子数
最終的にコレが求めたいのです。
物質の中にいったい何個の電子や原子が含まれているのか?
すでに物質中に含まれる原子の数は表せますね?
念のために確認する
$$
\color{#B22222}{
\pmb{
\begin{aligned}
\text{物質に含まれる原子数}&=\text{モル数}\cdot\text{アボガドロ数}\\[12pt]
&=\frac{\text{密度}ρ\cdot\text{体積}V}{\text{質量数}A}\cdot N_A\\[12pt]
&=\frac{ρ\cdot V}{A}\cdot N_A\\
\end{aligned}}}
$$
そこにもう1つ! 原子の中に含まれる電子数の表現を加味すれば・・・
$$
\color{#B22222}{
\pmb{
\begin{aligned}
\text{物質に含まれる電子数}&=\text{原子数}\cdot\text{原子番号}\\[12pt]
&=\frac{ρ\cdot V}{A}\cdot N_A\cdot Z\\
\end{aligned}}}
$$
となります。
ちなみに、物質に含まれる陽子の数も同じ式で表現することができます。
試験に出るのは「計算」より「概念」
計算が出ない訳ではないですが、文字式で関係性を問うものが多いです。
国試では「式のかたち」が問われやすい
国家試験では、いきなり計算をさせるというよりも、
「この式の構造を正しく理解しているか?」という観点で問われることが多くなっています。
たとえば次のような選択肢が並ぶ問題で、
どれが正しい式かを選ばせるタイプの出題がよく見られます。
- 質量×アボガドロ数 ÷ 原子量 × Z
- 密度×体積 ÷ 原子量 × Z × アボガドロ数
- 原子量 ÷ 質量 × アボガドロ数 × Z
一見どれももっともらしく見えるため、
「なんとなくZがあればいいでしょ」と思って選ぶと、まんまと引っかかってしまいます。
よくある引っかけ選択肢に注意!
特に注意したいのが、「原子量(=実際には質量数として扱う)とアボガドロ数の関係」に関する理解不足によるミス。
原子量の意味を「1個の原子の重さ」と思い込んでいると、式の組み立てが破綻してしまいます。
大切なのは、「式の意味」を分かって使うこと。
ちゃんと理解していれば、多少ひねった選択肢にも冷静に対応できますよ。
※本来は「原子量」という用語を用いるのが正解ですが、国家試験ではこの2つが混在して使われることがあります。
それは、実際の計算では原子量を整数化した「質量数」で近似することが多く、この方が式がシンプルになるからです。
当然、計算値も綺麗になりますよ。
実際の過去問を見てみよう。

2014年に実施された第66回国家試験からのご紹介。
第66回 2014年 問42
原子番号 $Z$ 、質量数 $A$ 、密度 $ρ\,\mathrm{g/cm^3}$ の物質 1 cm3中の 電子数はどれか。ただし、アボガドロ数を $N_A$ とする。
- $\frac{ρN_A}{ZA}$
- $\frac{ZN_A}{ρA}$
- $\frac{N_A}{ρAZ}$
- $\frac{ρZN_A}{A}$
- $\frac{ZAN_A}{ρ}$
いきなり電子数を問われると、「えっ?分かんない・・・」ってなってしまいがち。
でも大丈夫。いままでのプロセスをたどって考えていけば解けます。
答えを確認する。
正解は 4 です。
できましたか?
物質の中に含まれる電子数を問われていますから、物質中の原子数と原子番号の積で表現できます。
この問題では体積が1cm3となっているのがひっかけ要素ですね。
$$
\color{#B22222}{
\pmb{
\begin{aligned}
\text{物質に含まれる電子数}&=\text{物質に含まれる原子数}\cdot\text{原子番号}\\[12pt]
&=\frac{ρ\cdot V}{A}\cdot N_A\cdot Z\\[12pt]
&=\frac{ρ\cdot 1}{A}\cdot N_A\cdot Z\\[12pt]
&=\frac{ρ}{A}\cdot N_A\cdot Z\\[12pt]
\end{aligned}}}
$$
まとめ
電子数を直接「数える」ことはできなくても、
密度・質量数・アボガドロ数を使えば、式で電子数を導けるというのが今回のポイントでした。
ただし国試では、計算力よりも式の意味や関係性の理解が重視されることが多いです。
引っかけ選択肢に迷わされないよう、「1個の重さ」ではなく「全体との関係」で式を考える意識を持っておきましょう。

「1個の重さ」ではなくて、「全体の中の割合」として考えるのがコツだよ!
お願い
本サイトに掲載されている図やイラストの著作権は管理人にあります。
無断掲載や転載はお断りさせていただきます。
また、リンクフリーではありますが、画像などへの直リンクはお控えください。
次に読むならコレ!電爺的おすすめ内部リンク

ほれ、ここまで読んだんなら、次はこのあたりを見ておくとえぇぞい。
次に読むならコレ!たまのすけおすすめ外部リンク

ここまで読んできた皆さんなら、もう一歩踏み込んだ知識に触れてみたくなるはずです。そんな方におすすめの外部リンクを紹介しますね。

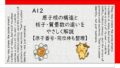
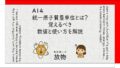
コメント