「電子にはいろんな種類があるって聞いたけど、自由電子と軌道電子の違いって結局なんなの?」
そう感じて、教科書を読んでもイメージが湧きにくい人は多いはずです。
この記事では、電子が原子核に束縛されているのか、外に飛び出しているのかという視点で、自由電子と軌道電子のちがいが分かるようになります。
イラストや日常の例えを交えながら、両者の特徴を整理し、試験でよく問われる「電子の分類」をシンプルに解説します。
自由電子と軌道電子は原子物理の基本中の基本であり、電気伝導や放射線のふるまいを理解するうえで必須の概念なので、ビシッと理解しましょう。
電子にはどんな種類があるの?
電子と聞くと、つい「原子のまわりを回っている粒子」というイメージだけで止まってしまいがちです。
でも、実際の物質の中では、電子は同じように見えても役割や振る舞いが異なります。
ここではまず、電子を大きく分類する視点を整理していきましょう。
中学校で習った「電子」の復習
電子といえば、中学理科で「原子のまわりを回っている小さな粒子」として学んだはずです。
マイナスの電気を帯びていて、陽子と電子の数が釣り合うことで、原子は電気的に中性を保ちます。
とはいえ、根っからの理系でもない限り、そんなこと覚えていないのも無理ありません。
忘れてしまったら、また覚えれば良いのです。
物質内の電子は2種類に分けられる
まず、一口に電子といっても、大きく2種類の電子に分けることができます。
高校以上のレベルになると、この電子を「自由電子」と「軌道電子」に分けて考えます。
一見するとどちらも同じ電子ですが、「どこに存在しているか」「どんな役割を持つか」が少しちがうのです。
既に出てきた「陰電子」・「陽電子」という違いではなく、物質の中のどこにあるかによって名称が変わってきます。
図を参照しながら見ていきます。
- 原子にしっかり束縛されている 軌道電子
- 束縛から外れて自由に動ける 自由電子
この2種類に分けて考えます。

物質の中には原子がたくさん詰まっていることはみなさんご存知のはずですね。
忘れてしまった方はA13:原子数と電子数の関係と計算式を図で整理|密度・原子量・アボガドロ数の使い方をチェック。

その原子の中に含まれる「軌道電子」と原子の外にある「自由電子」に分けることができます。
自由電子とは?
電子の中には、原子核のまわりにとどまらず、物質の中を動き回るものがあります。
こうした電子は、電気が流れる仕組みや金属の性質を理解するうえで、とても重要な存在です。
まずは「自由電子」がどんな電子なのか、基本から整理していきましょう。
原子に束縛されていない電子
自由電子とは、原子核の強い引力から解き放たれ、原子の外を動き回る電子のことです。
特に金属のような物質では、最外殻の電子(価電子)がしっかり束縛されず、原子から飛び出して周囲を移動できる状態になります。
言いかえると、自由電子は「ある原子の所有物」ではなくなり、物質全体を行き来できる共通の存在になるわけです。
自由電子は原子核に束縛されていませんので、物質内を比較的自由に動き回ることができます。
※実際には電子は何らかの束縛を受けるので、完全に自由な電子は存在しないようです。
仮定としての「自由」電子のようです。
まぁ、あまり気にせずに行きましょう。
自由電子が果たす役割
この性質こそが、金属が電気を通す理由です。
外部から電圧をかけると、自由電子は一斉に方向をそろえて移動します。
これが「電流」と呼ばれる現象です。
例えば、銅線の中では自由電子が絶えず動き回り、電気エネルギーを効率よく運んでいます。
逆に、自由電子がほとんど存在しないゴムや木材では、電子が流れる道がないため電気を通しません。
オレも牧場飛び出して放牧されたいわ~。


メシ食えなくなっても良いんかの?
そら考えもんやな。
牧場に残ってもええわ。

もう一つの重要な役割
自由電子は、電気伝導だけでなく「熱の伝わりやすさ」にも関係しています。
金属に触れるとひんやり感じるのは、自由電子が熱をすばやく運ぶからです。
このように、自由電子の存在は物質の性質そのものを決める重要なポイントなのです。
だから真夏は車の上で昼寝してられないのか。

そらアカンわ!
焼きネコになるで。

軌道電子とは?
すべての電子が自由に動き回っているわけではありません。
原子の中には、原子核のまわりにとどまり、決まった位置関係を保って存在している電子もあります。
ここでは、原子の構造を理解するうえで欠かせない「軌道電子」について整理していきましょう。
原子核に束縛されている電子
軌道電子とは、原子核の強い引力にとらえられ、決まった軌道(電子殻)を回っている電子のことです。
イメージすると、まるで太陽のまわりを惑星がぐるぐる回っているようなもの。
電子は「勝手に外に飛び出せない」かわりに、安定した位置に収まっているのです。
束縛されていることから、「束縛電子」と呼ぶ場合もあります。
※国試では「束縛電子」という名称は出てこないですね。古い主任者試験の過去問なら出会えるかもしれません。
軌道電子は元素や軌道で決まっているエネルギーで原子核に束縛されています。
この決まったエネルギーを結合エネルギーといいます。
電子殻と収容できる数(2n²則)
電子が収まる場所(軌道)は原子核に近い順に「K殻」、「L殻」、「M殻」、・・・のように続いていきます。
それぞれの殻に入れる電子の数は「2n²」というルールで決まります(n=殻の番号)。
- K殻(n=1):最大2個
- L殻(n=2):最大8個
- M殻(n=3):最大18個
外側へ行くほど、より多くの電子を収容できるようになります。
これを一般式で示すと 2n2 となります。
※nは主量子数といい、軌道の大きさを示したものです。K殻は n=1 、L殻は n=2 といった感じで、1ずつ増えていきます。
軌道電子はこのK殻やL殻といった軌道上にしか存在することはできません。
K殻とL殻の間のスペースには存在できないのです。
こういった連続的でないものを「離散的」と表現します。
また、各軌道の間隔は一定ではありません。
K殻とL殻の間が最も離れています。
次いでL殻とM殻の間が離れています。
お気付きですね?
外側に行けば行くほど、各軌道の間隔は「狭く」なっていきます。
つまり、外側に行けば行くほど、エネルギー準位差が小さくなっていきます。
※エネルギー準位については、A21:軌道電子のエネルギー準位とは?結合エネルギーとの違いをやさしく解説を参照してください。
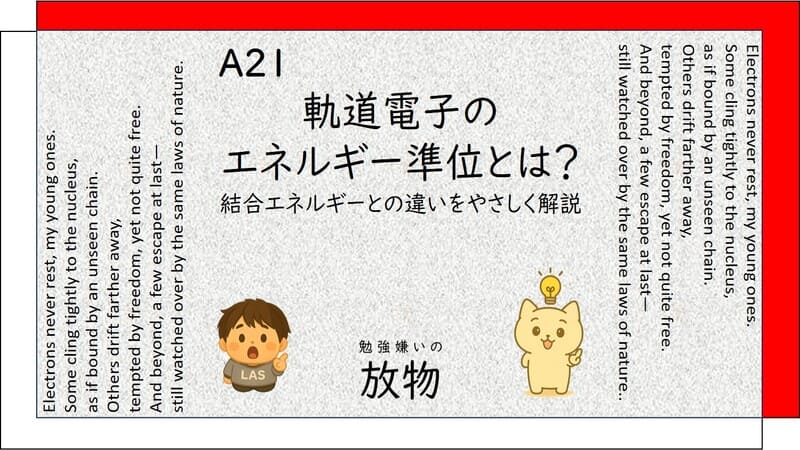
外側に行くほどどうなるのか?
電子のエネルギーを「束縛の強さ」で見ると、原子核に近い電子は強く引き寄せられているため、束縛エネルギーが大きい です。
一方、外側の電子は束縛が弱く、束縛エネルギーが小さい ので外に飛び出しやすい性質があります。
逆に、電子の位置を「エネルギー準位」として表すと、外側の電子ほどエネルギー準位が高い と言えます。
つまり、同じ「エネルギー」でも見方によって表現が逆転することに注意しましょう。
※束縛エネルギー=結合エネルギーです。
自由電子と軌道電子のちがいを整理しよう
ここまでで「自由電子」と「軌道電子」それぞれの特徴を見てきました。
では両者を並べて比べると、どんな違いがはっきりするでしょうか。
位置のちがい
自由電子は、原子から抜け出しており、特定の原子に属さずに物質全体を動き回っています。
一方、軌道電子は原子核のまわりにとどまり、決められた軌道(電子殻)の中で存在しています。
つまり、電子が「原子の中にいるのか」「原子の外を動いているのか」という点が、両者の大きな違いです。
束縛のちがい
自由電子は、原子核の引力からほとんど解き放たれているため、外部から電場が加わると比較的自由に動くことができます。
それに対して軌道電子は、原子核の引力に強く束縛されており、決まった殻の中から簡単に外へ出ることはできません。
この「束縛の強さ」の違いが、自由電子と軌道電子の性質を大きく分けています。
エネルギーの見方のちがい
電子のエネルギーを束縛の強さという視点で見ると、原子核に近い軌道電子ほど束縛が強く、束縛エネルギーは大きくなります。
一方で、エネルギー準位という表現を用いると、外側の軌道電子ほど高いエネルギー準位にあると考えます。
このように、「エネルギー」という言葉は、どの視点で見ているかによって意味が変わるため、混同しないよう注意が必要です。
実際の問題を見ていきましょう。
第62回 2010年 問42
L殻に存在できる軌道電子の最大数はどれか。
- 2
- 4
- 6
- 8
- 18
解答を確認する。
正解は 4 です。
「2n²則」を思い出せば迷うことなく選べるはずですよね。
L殻の主量子数nは2ですから、2×22=8となります。
医療現場でこの知識がどう役立つの?
自由電子と軌道電子の性質は、放射線技術の世界でも欠かせない知識です。
自由電子と放射線
放射線が物質を通過するとき、原子の外にある自由電子とぶつかってエネルギーを失うことがあります。
この相互作用が、線量計や半導体検出器で放射線を“数える”仕組みに直結しています。
また、X線管の中では金属の中の自由電子を加速し、陽極に衝突させることでX線を発生させています。
軌道電子と放射線
一方、放射線が原子の内側の軌道電子をたたき出すと、空いた軌道に別の電子が落ち込みます。
そのときに生じる余分なエネルギーが 特性X線 や 制動放射 として放出されるのです。
これらは医療画像の画質や被ばくの理解に直結します。
まとめ
電子は、見た目は同じでも「どこに存在しているか」によって役割が大きく変わります。
原子核のまわりに束縛され、決まった軌道(電子殻)に存在しているのが軌道電子。
原子核の束縛から外れ、物質の中を動き回っているのが自由電子です。
この区別を押さえておくことが、電気の流れや放射線と物質の相互作用を理解する第一歩になります。

原子核に束縛されていれば軌道電子、束縛されていなければ自由電子。
まずはこの整理をしっかりしましょう。
お願い
本サイトに掲載されている図やイラストの著作権は管理人にあります。
無断掲載や転載はお断りさせていただきます。
また、リンクフリーではありますが、画像などへの直リンクはお控えください。
次に読むならコレ!電爺的おすすめ内部リンク

ほれ、ここまで読んだんなら、次はこのあたりを見ておくとえぇぞい。
もっと知りたい方へ!たまのすけおすすめ外部リンク

ここまで読んできた皆さんなら、もう一歩踏み込んだ知識に触れてみたくなるはずです。そんな方におすすめの外部リンクを紹介しますね。
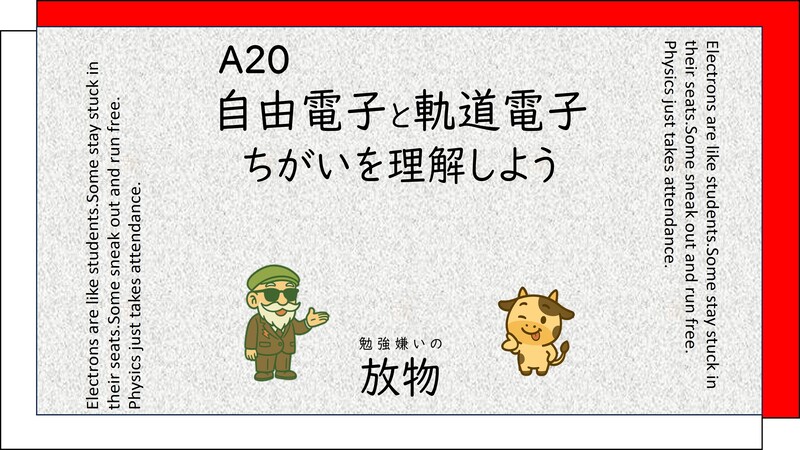
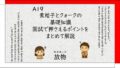
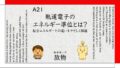
コメント