こんにちは。たなまるです。
特殊相対性理論、と聞いただけで「うわ、難しそう」「公式が複雑そう」って身構えてしまっていませんか?
でも大丈夫。
今回扱うのは、その“入口の入口”。
まずはイメージを掴むことが大切です。
計算問題でも狙われるポイントを押さえつつ、ふだんの世界とはちょっとちがう“高速世界”のルールを、ご紹介していきます。
この記事を読み終える頃には、あなたの中で“相対論”がちょっと身近に感じられるはずです。
特殊相対性理論ってどんな話?
特殊相対性理論というと「難しい理論」という印象を持たれやすいのですが、実は根っこにある考え方はとてもシンプルです。
それは “光の速さには、他のどんなものとも違う特別な性質がある” ということです。
私たちの日常では、物体の動きや時間の流れ方が変わるほどの高速現象を見ることはありません。
しかし、光に近い速さの世界では、時間や長さといった“当たり前”の感覚そのものが変化していきます。
この章では、相対性理論がどんな背景で生まれ、どのような人物によって作られたのかをご紹介します。
時代背景(当時の“常識”をひっくり返した理論)
1900年代の初めごろ、人々は「光は“エーテル”と呼ばれる見えない物質の中を伝わっている」と考えていました。
これは、海の中を波が進むように、光も何かの“媒体”が必要だろうという当時の常識に基づいた考え方です。
しかし、光の速さを正確に測ろうとした実験(マイケルソン・モーレーの実験)では、観測者がどう動いても光の速さが変わらない という結果が得られました。
この結果は、当時の物理学の枠組みでは説明できない「異常な現象」でした。
科学者たちは深い混乱に陥り、「従来の考え方をそのまま使い続けることはできない」と感じ始めていました。
今までの常識が通用しなくなってしまったんですね?


そうなんだよ。
科学者たちは困ったと思うよ。
分かるで。
いままで大盛牛丼が食えた額で並盛しか食えへん感じやな。
そりゃ確かに困んで。


常識のレベルが全然違うけどね・・・
アインシュタイン博士について
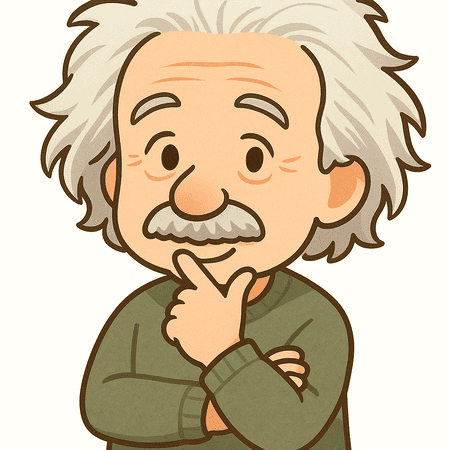
そんな時代に登場したのが、若き日のアインシュタイン博士です。
博士は特別な研究施設で実験をしていたわけではなく、特許局で働きながら独自に物理を考えていた人物でした。
アインシュタイン博士は、当時の常識にとらわれず、次のように発想しました。
「光の速さが変わらないという実験結果を、最初から“事実”として受け入れてみよう。」
この“前提のひっくり返し”こそが、特殊相対性理論の原点です。
博士は、真空中の光速を「どんな観測者から見ても一定」と仮定し、その結果として時間や長さが変化する世界の仕組みを理論としてまとめました。
当時としては非常に大胆で、従来の物理学を根本から書き換えるような提案でしたが、後の観測・実験は次々とアインシュタイン博士の理論を支持し、今では物理学の基盤となっています。
① 慣性系座標とは?
特殊相対性理論を理解するうえで、まず押さえておきたいのが 「慣性系座標」 という考え方です。
少し難しそうに聞こえますが、内容はとてもシンプルで、「動いている人から見ても、止まっている人から見ても、物理のルールは同じように成り立つ」という考え方を表しています。
日常の例で言えば、静かな電車に乗っていると、車内でボールを上に投げても普通に手元へ戻ってきますよね。
電車が動いているからといって、ボールが変な方向へ飛んでいったりはしません。
このように、「動いている人でも物理法則が同じように見える世界」のことを 慣性系 と呼びます。
動いていても“物理法則が普通に成り立つ世界”のこと
慣性系の考え方は、「物体に特別な力が加わっていない状態なら、どんな観測者から見ても物理の基本ルールは変わらない」というものです。
たとえば、自分が自転車でまっすぐに走っているとして、その上でコインを落とすと、コインは自転車と同じ方向へ進みながら地面に落ちます。
どこか“特別にねじ曲がった物理法則”が働くわけではありません。
このように 「一定の速さでまっすぐ進んでいるとき、物理法則は変わらない」 という前提が、慣性系の基本になります。
特殊相対性理論では、まずこの“共通の土台”の上に話が進んでいきます。
相対論の土台として知っておきたいポイント
特殊相対性理論では、いろいろな“高速の世界”の不思議な現象が登場しますが、それらはすべて 「慣性系同士を比べる」 という前提で説明されます。
このとき大切なのは次の2点です。
- 慣性系どうしはどちらが正しい・間違っているということはない
→ どちらの視点も等しく扱われる。 - そこから見た光の速さが、常に一定として扱われることが前提
→ 後で学ぶ「光速度不変の法則」へつながる。
つまり、慣性系という考え方は、特殊相対性理論の“舞台装置”のような役割を果たしています。
もし慣性系という共通の土台がなければ、光速が一定なのかどうかを公平に比べることもできなくなります。
特殊相対性理論を学ぶうえでは、まず「慣性系とは、物理のルールが普通に働く座標のこと」というイメージを持っておけば十分です。
② 光速度不変の法則とは?
特殊相対性理論の中心にあるのが、光の速さは真空中であれば誰が見ても変わらない という法則です。
「そんな不思議なことが本当にあるの?」と感じるかもしれませんが、これは実験で繰り返し確かめられている確かな事実です。
ふつう、私たちがボールや車を見ると、見る人の動きによって速さの受け取り方が変わります。
しかし光だけは例外で、
光源が動いていても、受け取る側が動いていても、その速さは一定(約 3.0×10⁸ m/s)
になります。
この“変わらなさ”が特殊相対性理論を支える柱であり、後に学ぶ時間や長さの変化、質量とエネルギーの関係など、すべての基盤になっています。
真空中の光の速さは“誰が見ても”変わらない
光速度不変の法則が示しているのは「真空中の光の速さ c は、どんな観測者から見ても同じ」という一点です。
たとえば、光を出すライトを高速で走る車に取りつけたとしても、「光が車の速さぶんだけ速く見える」ということは起きません。
これは、私たちの感覚からするととても不自然に感じますが、実験ではいつも同じ結果が出ます。
この“光の特別な性質”を素直に受け入れて、そのうえで物理のルールを書き換えたのがアインシュタイン博士の特殊相対性理論だと言えます。
物質中で光が遅くなる理由と $\pmb{\frac{c}{n}}$ の関係
ここで一つ注意したいのは、「光の速さが一定なのは“真空中”に限る」という点です。
空気・水・ガラスなど、物質の中を通る光は真空中よりも遅くなります。
たとえば水の中では、光は真空中の約 1/1.33 の速さになります。
これは光が物質の中で 原子と相互作用をしながら伝わる ため、見かけ上ゆっくり進むように見えるからです。
物質中での光の速さは、次の式で表せます。
物質中の光速度 = $\pmb{\frac{c}{n}}$
(n:屈折率)
ここで言っているのは「真空中の光速そのものが変わった」のではなく、
物質の中では光が“進みにくくなる”というだけ、という点です。
つまり、
- 真空中の光速は絶対に変わらない(光速度不変)
- 物質中では光がゆっくり進む$\pmb{\frac{c}{n}}$
という2つの事実は矛盾していない、ということになります。
③ 質量エネルギーとは?
特殊相対性理論の中でも特に有名なのが、アインシュタイン博士の式
$$\pmb{E = mc^2}$$
です。
私たちが“質量”と呼んでいるものの中には、実はエネルギーがたくさん詰まっています。
この式は、そのエネルギー量を「質量 m と光速 c を使って計算できますよ」ということを表しています。
少し抽象的に聞こえるかもしれませんが、考え方はいたってシンプルで、
「質量があるものは、それだけでエネルギーを持っている」
ということを示しています。
ほな、オレもエネルギーもっとるんか?


いっぱい持っているんじゃないかのぅ。
$\pmb{E = mc^2}$ が意味する「質量に詰まったエネルギー」
“質量の中にエネルギーが詰まっている”というのは、日常生活ではなかなか実感しにくい考え方です。
しかし、質量をものすごく小さくして、そのエネルギーを取り出すことができれば、非常に大きなエネルギーを得られます。
たとえば「1 g の物質にどれくらいのエネルギーがあるのか」を考えてみると、光速(約 3.0×10⁸ m/s)を2乗するだけで、とてつもなく大きな数になります。
$E = mc^2$ が示しているのは、
質量は、光速の2乗という大きな倍率を通して莫大なエネルギーに換算できる
ということです。
この考え方は、原子力や放射線の世界で重要な意味を持っています。
電子の質量をエネルギーに換算する考え方
放射線分野では「電子1個の質量をエネルギーに換算するとどれくらいか」という値をよく使います。
電子の質量 m を式 $E = mc^2$ に代入すると、
電子1個分のエネルギーは 0.511 MeV
として表されます。
この値は放射線物理の多くの場面で登場し、
- ガンマ線の相互作用
- ペア生産
- 電子線の性質
などを理解するうえで基準となる重要な数値です。
ここでは「電子の質量をエネルギーに換算すると 0.511 MeV になる」という事実だけ押さえておけば十分です。
詳しい導出はココを展開してください。
$E=mc^2$ はエネルギーを J (ジュール) で定義した関係式です。
そのため、 J を eV に変換しなければいけません。
そこはA3:放物シリーズ完全対策!力学的エネルギーとその単位(J・eV)をわかりやすく解説をご参照ください。

ここでは電子の質量を $m_e=9.1093 \times 10^{-31} \:\mathrm{[kg]}$ 、真空中の光速度を $c=2.99792 \times 10^8 \:\mathrm{[m/s]}$と普段より厳密な値を用いて計算していきます。
$$
\begin{aligned}
E&=m_ec^2\\[8pt]
&=9.1093 \times 10^{-31} \times {(2.99792\times 10^8)}^2\\[8pt]
&=8.19 \times 10^{-14} \:\mathrm{[ J ]}\\[8pt]
&=\frac{8.18700 \times 10^{-14}}{1.602 \times 10^{-19}}\\[8pt]
&=511049 \:\mathrm{[ eV ]}\\[8pt]
&=0.511 \:\mathrm{[ MeV ]}\\
\end{aligned}
$$

単位換算がポイントです。
④ ローレンツ変換とは?
光の速さがどんな観測者から見ても変わらない、という光速度不変の法則を前提にすると、
それまでの物理では説明できない新しい現象がいくつも出てきます。
たとえば、物体が高速で動くと、
- 動いている側から見ると時間の進み方がゆっくりになる
- 動いている物体の長さが短く見える
など、ふだんの生活では感じることのない現象が起こります。
これらの不思議な“見え方の変化”をきちんと計算で扱えるようにしたのが、
ローレンツ変換(Lorentz transformation) です。
高速で動くと時間や長さの“見え方”が変わる理由
ふつうの世界では、時間はだれにとっても同じ速度で進み、物体の長さも変わりません。
しかし光速に近い速さで動くと、これらが変化して見えるようになります。
これは、光速度不変の法則が成り立つためには、
観測者の動きによって時間や長さのほうが変わらなければつじつまが合わない
からです。
たとえば、あるロケットが光速に近い速さで飛んでいたとしましょう。
外から見るとロケットの中の時計はゆっくり進み、ロケットの全長も短く見えます。
これが 時間の遅れ(time dilation) と 長さの収縮(length contraction) です。
ローレンツ変換は、このような現象を正確に記述するための“変換ルール”だと考えるとイメージしやすいです。
ローレンツ因子 $\pmb{γ}$ の役割(式の形だけ押さえる)
ローレンツ変換で重要な役割を果たすのが、
ローレンツ因子 γ(ガンマ) です。
これは次の式で表されます。
$$
\pmb{
γ=\frac{1}{\sqrt{1-(\frac{v}{c})^2}}
}$$
$$
\begin{aligned}
{v} & : \text{物体の速度} \\
{c} & : \text{光の速度(約 }3.0 × 10^8 \text{ m/s )}
\end{aligned}
$$
$v$ が光速に近づくほど分母が小さくなり、$γ$ はどんどん大きくなります。
この $γ$ を使って、時間がどれだけ遅くなるか、長さがどれだけ縮むかを計算します。
ただし、この式を完全に覚える必要はありません。
この記事で押さえたいのは次の一点です。
高速で動くと、時間と長さの見え方は $\pmb{γ}$ を使って決まる。
これだけ理解できれば、特殊相対性理論におけるローレンツ変換の“役割”としては十分です。
未来へ行くタイムマシンは「現実の物理」で説明できる?
ローレンツ変換では、高速で移動する物体の時間がゆっくり進むという「時間の遅れ」が起こります。
これは空想の話ではなく、粒子実験などで実際に確かめられている現象です。
もし光速に近い速さで宇宙旅行をすると、宇宙船の中では1年しか経っていないのに、地球では数年、あるいはそれ以上の年月が流れていることがあります。
これはつまり、宇宙船に乗っていた人が“地球の未来へ進んだ” ということです。
この意味で、特殊相対性理論は
「未来へ行くタイムマシンなら理論的に可能」
という結論を示しています。
一方、過去に戻ることは特殊相対性理論ではできません。
原因と結果の順番が逆転してしまうため、理論そのものが成立しなくなるからです。
それでも「未来へなら行ける」という事実は、相対性理論の魅力を感じるうえでとても大きなポイントです。
国試で紛れ込む誤りの枝候補
特殊相対性理論に関する問題では、正解となる知識は
- 慣性系座標
- 光速度不変の法則
- 質量エネルギー
- ローレンツ変換
の4つがほとんどです。
国試ではこれらを並べて、“1つだけ違うものを選ぶ”タイプの出題がよく見られます。
このとき、誤りの枝としてよく混ざるのが 黒体輻射(こくたいふくしゃ) です。
黒体輻射
黒体輻射は、物体が温度に応じて放射する光(電磁波)の性質を扱う分野で、
相対性理論ではなく 量子力学 と深い関係があります。
黒体とは“すべての光を吸収する理想的な物体”のことで、その温度が高くなるほど強い電磁波を放射します。
そして、この“放射の強さと波長の関係”を説明する理論が黒体輻射です。
一方、特殊相対性理論は
「光速は一定」「高速での時間や長さの変化」
といった“運動の速さ”に関する法則です。
黒体輻射とは扱っている物理現象の分野がまったく違います。
国試では、
「特殊相対性理論に関係のあるものを選べ」
という問題で 黒体輻射が混ぜられやすい ので、
“黒体輻射=量子の話であって、相対論とは無関係”
という点を押さえておくと安心です。
実際の問題を見ていきましょう
第58回 2006年 午後43
特殊相対性理論に直接関係ないものはどれか。
- 慣性系
- 黒体輻射
- 光速度不変
- 質量エネルギー
- ローレンツ変換
2006年に実施された第58回からのご紹介。
しっかりとこの記事をお読みいただけた方なら、すんなりと解けるはずですね。
解答を確認する。
正解は 2 です。
何を隠そう、ワタクシたなまるが受けた国試がこの第58回です。
今回の記事はこの問題を解くために書いたようなものです。
見ていただいてお分かりのように、現象の中身までは言及されません。
関係のある項目さえ分かっていれば得点できます。
当然ながら、関係ないのは 黒体輻射 ですね。
黒体輻射とは、高温の物体が出す光のことです。
たとえば、熱くなった鉄が赤く光るのも黒体輻射の一例です。
物理の歴史では、この現象の説明が難しく、19世紀末に「紫外破綻(しがいはたん)」という矛盾が発生しました。
この問題を解決するために、プランクが「量子」の考え方を導入し、後の量子論につながりました。
つまり、黒体輻射は量子論の始まりに関する話であり、特殊相対性理論とは別の分野です。
医療現場での関わり
今日の内容が医療現場のどこで応用されているかというと・・・
放射線治療における陽子線・重粒子線です。

- 陽子線治療や重粒子線治療では、粒子が光速に近い速度で加速されます。
- このとき、相対論的質量増加や時間の遅れといった相対性理論の効果を考慮しないと、正確な照射計算ができません。
相対性理論を理解することが、治療精度の向上につながるというわけなんです!
まとめ
特殊相対性理論は「光の速さはどんな観測者から見ても変わらない」という、一見シンプルに見える法則から広がった理論です。
その前提を守るために、時間や長さといった“当たり前の量”のほうが変化するという、直感に反する結論が導かれます。
この記事で扱った
- 慣性系座標
- 光速度不変の法則
- 質量エネルギー
- ローレンツ変換
の4つが押さえられれば、国試で問われる特殊相対性理論のポイントは十分理解できます。
また、紛れ込みやすい黒体輻射は量子力学の話であり、相対論の範囲外であることも覚えておきましょう。
相対論は“高速の世界の物理”ですが、基礎の部分だけなら難しい数式は必要ありません。
不思議さと面白さの両方を感じながら、少しずつ馴染んでいってほしいと思います。

相対論って聞くと身構えがちだけれど、今日の4つが分かれば土台はもうできているよ。
この先でローレンツ因子の計算に触れる場面は出てくるけれど、背景の理論まで深く追う必要はないんだ。
まずは“こういう世界なんだ”とイメージできていれば、それだけで十分だからね。
次に読むならコレ!電爺的おすすめ内部リンク

ほれ、ここまで読んだんなら、次はこのあたりを見ておくとえぇぞい。
次に読むならコレ!たまのすけおすすめ外部リンク

ここまで読んできた皆さんなら、もう一歩踏み込んだ知識に触れてみたくなるはずです。そんな方におすすめの外部リンクを紹介しますね。
光の速さはなぜ一定?(NHK for School)
「光速が一定という性質が、どれだけ不思議なことなのかをアニメで楽しく学べます。」
DOE Explains… Relativity(米エネルギー省)
「質量とエネルギーの関係や、光速の定数性。専門家が易しくまとめています」
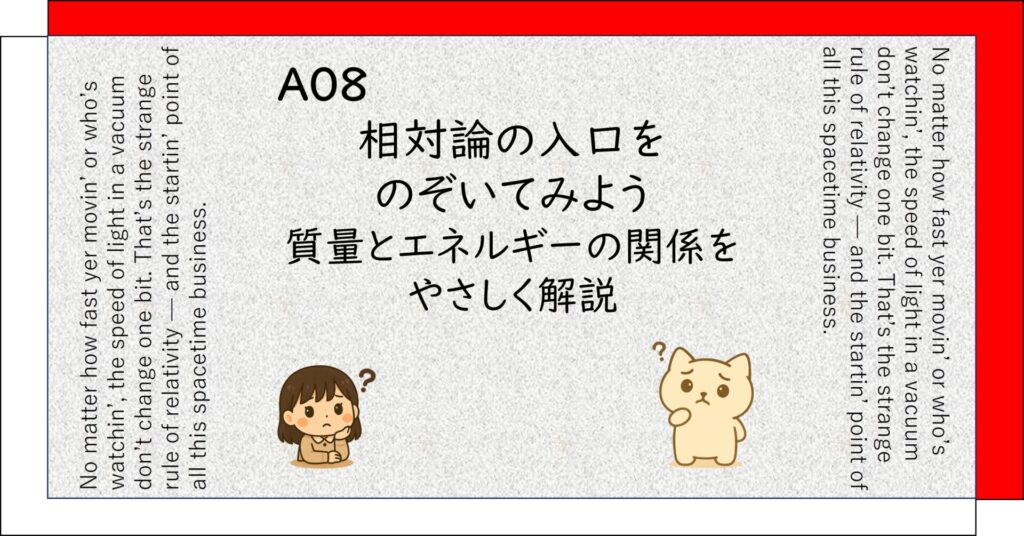

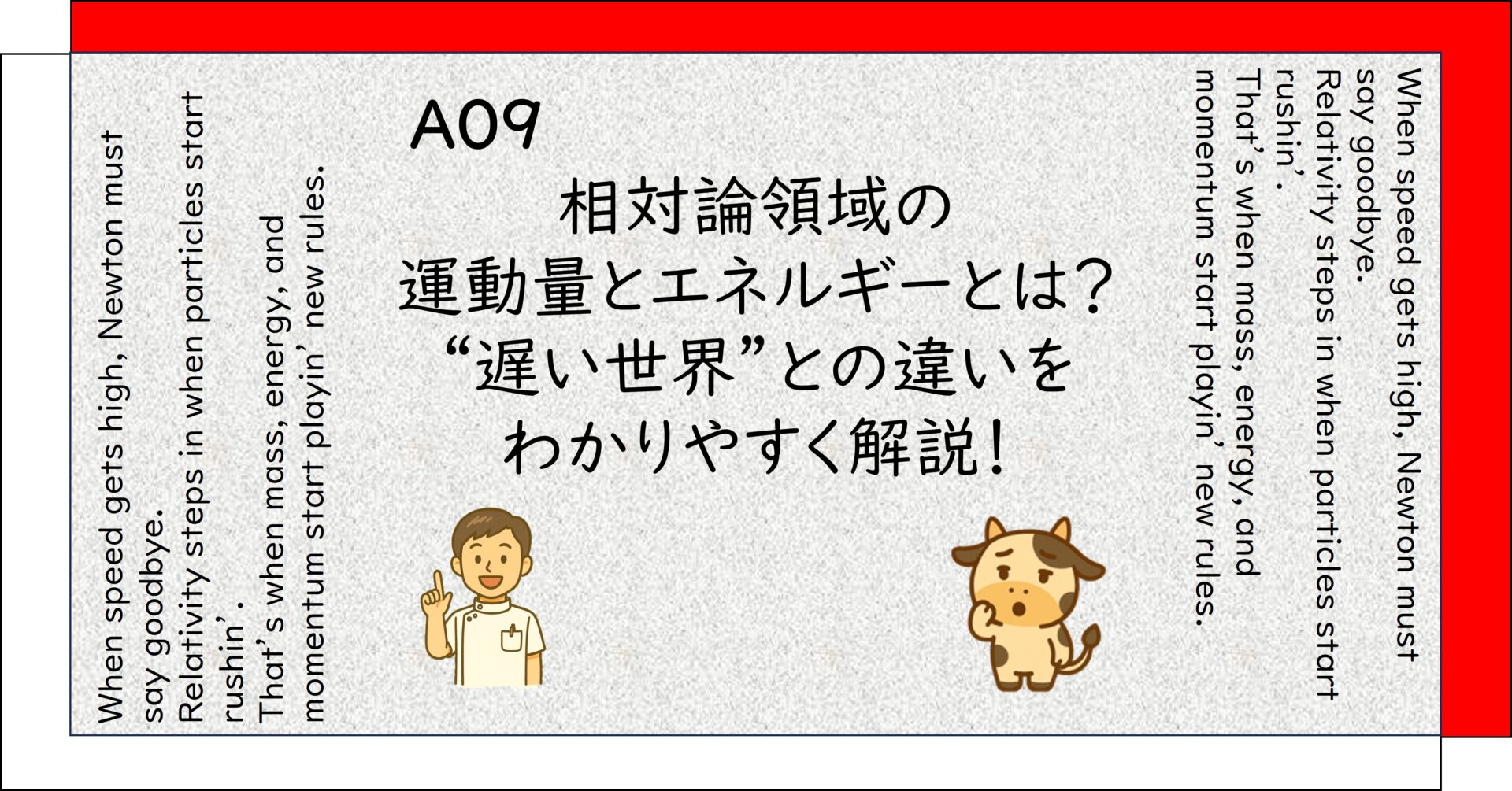
コメント