こんにちは。たなまるです。
放物に限った話ではありませんが、放射線の勉強をしていくと、放射線にはいくつか種類があることが分かります。
α線、β線、γ線、X線・・・
その中でも我々が最も利用する放射線はX線です。
X線を理解するには、まず“波”のことを思い出しておくのが大切です。
高校で物理学を学んだ方は何となく覚えている方も多いでしょう。
学んだけど、力学と違って好きじゃないんだよね・・・って方もいるでしょう。
(ワタクシ、たなまるはこのパターンでしたね。それが今は講師として皆さんにお伝えする側になっていることに「人生の面白さ」が詰まっている気がします。)
そもそも、物理取ってないんですけど・・・これまた最近の学生さんに多いパターン。
高校3年になってから放射線技師を目指した方たちには、科目選択の時点で物理は避けられてしまうケースが多いですね。悲しいけど、これが現実でしょう。
そんな方はこちらの記事で波の基礎をカバーしていきましょう。
波が苦手で不安だという方も、大丈夫。
高校物理で学ぶ「反射波」などは扱いませんので、新しいジャンルのつもりで気軽に覗いてみてください。
分かりやすくポイントを押さえてお伝えしていきます。
X線は横波?縦波? まずは波の種類を整理しよう

波には大きく分けて「縦波」と「横波」の2種類があります。
これは、“振動の向き”と“波の進む向き”の関係によって分類されます。
| 波の種類 | 振動の向き | 波の進む向きとの関係 | 主な例 |
|---|---|---|---|
| 縦波 (Longitudinal wave) | 波の進む向きと同じ | 並行 | 音波、地震のP波 |
| 横波 (Transverse wave) | 波の進む向きと直角 | 垂直 | 光、X線、地震のS波、水面の波 |
例えば、エコー検査に用いる超音波は進行方向が空気分子の振動とおなじ前後方向なので縦波です。
一方、X線や光のような電磁波は、電場と磁場が進行方向と直角に振動しているため、横波に分類されます。
この超音波は縦波、X線は横波という部分は私が学生時代に良く国家試験に出題されました。
20年以上前に流行った定番の出題です。あぁ懐かしや。最近は見ませんな・・・
X線は横波なので、ここからは横波の解説をしていきます。
波って何?X線の理解に必要な「波の基本」
X線は、粒のような性質と同時に「波」としての性質も持っています。
つまり、X線の本質を理解するためには、この「波」とは何かをしっかりと押さえておく必要があります。
まず最初に確認しておきたいのは、「波」という現象がどのようなものかという基本的なイメージです。
ここでいう「波」は海の波のように見える現象だけではなく、音や光、電波などさまざまな形で現れるものです。
X線もまた、波としての性質を持つ放射線の一つに含まれます。
この章では、そんな波の基礎を「見てわかる」「数式でつかめる」ように、4つのポイントに分けて整理していきます。
「波」ってどんなもの?
![波の基本構造を示す図。山と谷が繰り返される波形に対し、波長λ[m]、周期T[s]、振幅、進行速度v[m/s]が矢印や記号で示されている。横軸は時間または距離。](https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/06/A05 波-1024x579.png)
まずは、上の図を見てみましょう。
これは“典型的な波”の形をイメージしたものです。まるで海の波のように、上に盛り上がった部分(山)と、下にくぼんだ部分(谷)が交互に並んでいますね。
この波は「変位」と呼ばれる量が時間とともに変化していく様子を表しています。
変位とは、ある基準からどれだけズレているかという量のことです。上下に振れているこの波は、何らかの“揺れ”が時間や空間に伝わっていく様子を表していると考えてください。
そして、波には必ず「伝わる方向」があります。図の右向きの矢印が、波が伝わっていく向きを示しています。
このように、波とは“揺れ(変位)”が時間や空間に沿って広がっていく現象なのです。
波の3大要素:振幅・波長・周期
波の3大要素を説明していきます。
こういった基礎知識を疎かにしてしまうと、それ以降の知識が入りにくくなりますから、しっかりと抑えていきましょうね。
振幅(しんぷく)
![波の基本構造を示す図。山と谷が繰り返される波形に対して、波長λ[m]、周期T[s]、進行速度v[m/s]が記されている。特に振幅が赤色の矢印と文字で強調されている。](https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/06/A05 波 振幅-1024x579.png)
波の山の高さが、赤い矢印で示されています。これが振幅です。
振幅とは、波の基準線(中心)から山の頂点までの高さ、または谷の底までの深さのことを指します。
つまり、どれくらい大きく揺れているかを表す値です。
振幅が大きい波ほど、“強さ”や“エネルギー”が大きくなります。
逆に、振幅が小さい波は揺れ幅が小さく、エネルギーも少ないということになります。

ちなみに、音の場合は振幅は「音の大きさ」を表すことになります。

おっ、さすが趣味がギターだけのことはあるの。
波長(はちょう)
![波の基本構造を示す図。山と谷が繰り返される波形に対して、波長λ[m]、周期T[s]、進行速度v[m/s]、振幅などが記されている。特に波長λ[m]と距離[m]が赤字と矢印で強調されている。](https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/06/A05 波 波長-1024x579.png)
図の赤い矢印が示しているのが、波長です。
山から次の山まで、あるいは谷から次の谷まで――この「同じ形の位置」同士の間隔を波長と呼びます。
つまり波長とは、波が1回ぶん揺れ終わるまでに進む距離のことです。
波が空間にどのように広がっているかを表す量で、単位はメートル(m)で表します。
波長が長ければ、それだけ波の「山と山の間」が広く、
波長が短ければ、山と山の間がキュッと詰まっている――そんなイメージでOKです。

単位は m とはいうものの、放射線は10-9 m 程度と非常に短いんです。
もう見えんのとちゃう?

周期(しゅうき)
![波の構造を説明する図。山と谷の繰り返しを通して、周期 T[s]、波長 λ[m]、振幅、変位、速度 v[m/s] が示されている。特に周期 T[s] と時間[s] のラベルが赤字で強調されている。](https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/06/A05 波 周期-1024x579.png)
図の赤い矢印で示されているのが、周期です。
これは、波が1回ぶんの揺れを終えるのにかかる時間のことを表しています。
たとえば、山から次の山まで進むのに1秒かかったとすれば、その波の周期は「1秒」です。
単位は「秒(s)」で表します。
この周期は、波がどれくらい速いペースで振動しているかの指標になります。
短い周期なら、波は細かく速く振動していますし、周期が長いと、ゆっくり大きく揺れている波になります。

波が1回ゆれるのに何秒かかるか、それが「周期」ってことです。
振動数とHzの意味もおさえよう
![水平軸を時間 [s] とし、1秒間に繰り返される波形を描いた図。1 [s] の区間に複数の波が含まれており、1秒あたりの波の数=振動数(周波数)を示している。ラベルは「振動数(周波数)」。](https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/06/A05 波 振動数-1024x430.png)
波が1回振動するのにかかる時間を「周期」といい、1秒間に何回振動するかを「振動数」といいます。
この2つの関係は、次の式で表されます。
$$
f=\frac{1}{T}
$$
周期の単位は「秒(s)」であり、振動数の単位は「ヘルツ(Hz)」です。
これは「1秒間に○回振動する」という意味であり、「1/s」と表すこともあります。
別の言い方をすれば、「1秒間に波が〇回くる」と表現することもできます。
波の速さと「v=fλ」の関係
波の速さは、次の式で表されます。
$$
v=fλ
$$
ここで
$v$ は波の速さ(単位は「m/s」)、
$f$ は振動数(単位は「Hz(ヘルツ)」=「1/s」)、
$λ$ は波長(単位は「m」)
です。
では、この式がどう成り立つのか、単位の視点から見てみましょう。
振動数 $f$ は「1秒間に○回揺れる」または「1秒間に〇回の波が来る」という意味でした。
波長 $λ$ は「1回の揺れ(波)で進む距離」です。
つまり、1秒間にくる波の数×1波あたり〇メートルなので、1秒間で進む距離が求められます。
$$
\begin{aligned}
v&=fλ\\[6pt]
[\frac{m}{s}]&=[\frac{1}{s}]\times [m]
\end{aligned}
$$
結果として、波の速さ $v$ の単位 m/s と一致します。
式の意味だけでなく、単位を見てもこの関係が自然であることがわかりますね。
エネルギーと運動量の式をマスターしよう
波には、振動するという性質のほかに、「エネルギーを運ぶ」という重要な特徴があります。
X線のような電磁波も、目に見えなくても確かにエネルギーを持っていて、それが物質に当たることでいろいろな反応を引き起こします。
ここでは、そのエネルギーや運動量について、数式を通して確認していきましょう。
プランク定数とエネルギーの関係式
X線などの電磁波は、「波」であると同時に「粒」としての性質も持っています。
このときの粒を「光子(こうし)」といい、光子が持つエネルギーはプランク定数と振動数の積で表されます。
$$
E=hν
$$
$$
\begin{aligned}
{E} & : \text{エネルギー[ J ]} \\
{h} & : \text{プランク定数[ Js ]} \\
{ν} & : \text{振動数[ 1/s ]}
\end{aligned}
$$
この関係式は、光子1個あたりのエネルギーが、振動数に比例することを示しています。
つまり、振動数が高いほど、エネルギーも大きくなるということです。
また、波の速さ $v$ と振動数・波長の関係 $c=νλ$ を使うと、エネルギーは波長からも求められます。
$$
E=hν=\frac{hc}{λ}
$$
ここで、波長 $λ$ の単位は m なので、式の単位も併せて確認しておきましょう。
$$
\begin{aligned}
E&=\frac{hc}{λ}\\[6pt]
[J]&=[\frac{Js \times \frac{m}{s}}{ m }]
\end{aligned}
$$
こちらもエネルギーの単位「ジュール」になります。
波の運動量と光子の性質
光子は質量を持ちませんが、運動量を持っています。
この運動量は、エネルギーや波長と関係のある式で表すことができます。
$$
p=\frac{E}{c}
$$
$$
\begin{aligned}
{p} & : \text{光子の運動量[ kg・m/s ]} \\
{E} & : \text{エネルギー[ J ]} \\
{c} & : \text{光速度[ m/s ]}
\end{aligned}
$$
エネルギーの式 $E = hν$ を代入すると、次のように表せます。
$$
p=\frac{E}{c}=\frac{hν}{c}
$$
さらに、$c = νλ$ の関係を使うと、波長との関係も次のように表せます。
$$
p=\frac{E}{c}=\frac{hν}{c}=\frac{h}{λ}
$$
この式の単位を見てみましょう。
プランク定数 h の単位は「J・s」、波長 λ の単位は「m」なので、
$$
\begin{aligned}
p&=\frac{h}{λ}\\[6pt]
[kg\cdot \frac{m}{s}]&=[\frac{Js}{m}]\\[6pt]
&=[\frac{kg \cdot \frac{m^2}{s^2}\cdot s}{m}]\\[6pt]
&=[kg \cdot \frac{m}{s}]
\end{aligned}
$$
これは運動量の単位と一致します。
運動量はエネルギーを速度で除すことで求めることができます。
その結果、プランク定数を波長で除したものと等しくなります。
ここでは、エネルギーの単位 J を SI 基本単位に分解するテクニックを使いました。
この J の分解は結構便利ですので、忘れてしまった方はA04:主任者試験対策:SI単位の「分解」パターン4選【ジュールも解説】も併せてご参照ください。
実際の問題を見ていきましょう。
元ネタが第48回(1996年)と古いので、少しカスタマイズしております。
練習問題として捉えて下さい。
練習問題
次の記述で正しいのはどれか。2つ選べ。
ただし、プランク定数を $h$ 、光速度を $c$ とする。
- 波長 $λ$ の光子の運動量は $\frac{h}{λ}$ である。
- 運動量 $p$ を持つ粒子の波長は $\frac{h}{p}$ である。
- 振動数 $ν$ の光子のエネルギーは $\frac{h}{ν}$ である。
- 波長 $λ$ の光子のエネルギーは $\frac{hλ}{c}$ である。
- 速度 $v$ 、質量 $m$ の粒子の全エネルギーは $\frac{mc^2}{\sqrt{1-(\frac{c}{v})^2}}$ である。
解答を確認する。
答えは 1と2 です。
解説
元ネタは第48回(1996年)とかなり昔の問題です。
かなり古いのですが、基本要素がたくさん詰まってますので、採用してみました。
- 波(光子)の運動量と波長の関係性を聞かれています。覚えましょう。正しい記述です。
- 1に似ていますが、粒子の場合を聞かれています。ただ、関係性は波の場合と同様に考えてOKです。覚えましょう。正しい記述です。
- 光子のエネルギーと振動数の関係性を聞いています。E=hνです。
- 光子のエネルギーと波長の関係性を聞いています。E=hc/λです。
- ローレンツ因子を用いた粒子のエネルギーの表し方を聞いています。分母のルート内にあるvとcの位置関係が逆になっています。c/vとなっていますが、正しくはv/cです。
医療現場でこの知識がどう役立つの?

医療現場で波?と思うかもしれませんが、我々の扱う超音波やX線も波の一種です。
つまり、波を使った検査なんです。
波の特性を理解してX線を適切に利用できるようにならなければなりませんね。
我々の領域以外でも心電図や脳波なんかは波形で示されます。
やはり波と医療には深い関係があるんですね。
まとめ
X線の性質を理解するためには、「波」というものの基本的な特徴をしっかりと押さえておくことが大切です。
波には、振幅・波長・周期・振動数などの物理量があり、それぞれが互いに関係し合っています。
波の速さは「$v = fλ$」で表され、振動数や波長から求めることができます。
また、X線のような電磁波は、波でありながらエネルギーや運動量をもつ「粒(光子)」としても振る舞います。
エネルギーは「$E = hν = \frac{hc}{λ}$」、運動量は「$p = \frac{E}{c} = \frac{hν}{c} = \frac{h}{λ}$」で表され、どちらも波の性質と深く関係しています。
これらの基本を理解しておくことが、X線の吸収や散乱、撮影原理などを学ぶうえでの土台になります。

波って難しく感じるかもしれませんが、エネルギーと運動量の表し方が問われるくらいです。
次に読むならコレ!電爺的おすすめ内部リンク

ほれ、今回の計算がちとむずかしかったと思うたら、こっちも見ておくとええぞい。
次に読むならコレ!たまのすけおすすめ外部リンク

ローレンツ因子のこと、もっと深く知りたくなったでしょ?
僕が厳選したリンクを紹介するよ!
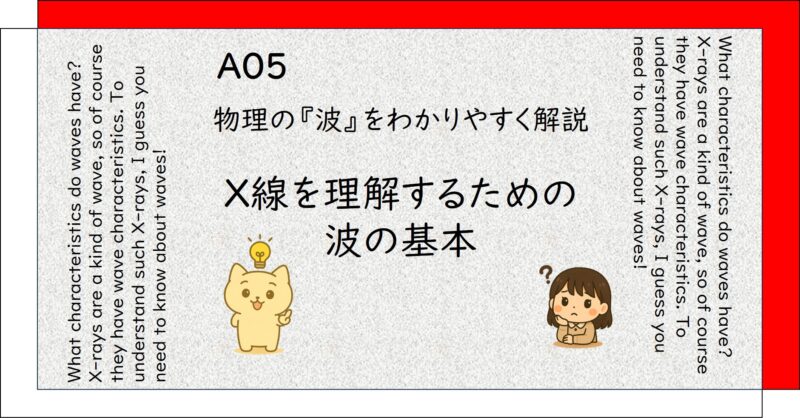
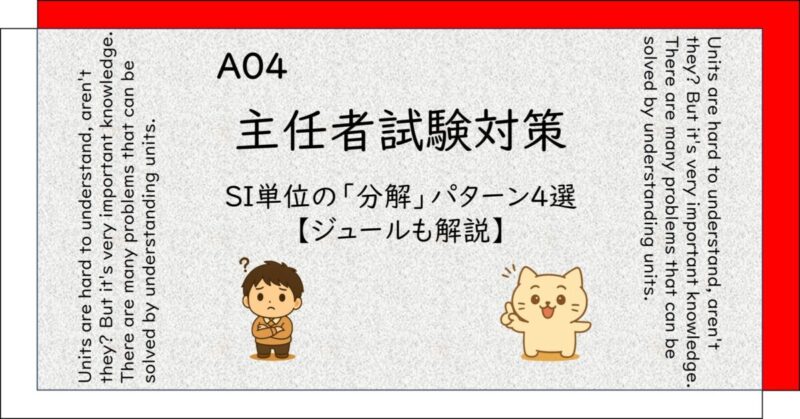

コメント