「微粒子の質量って小さすぎて、キログラムやグラムで表すとピンとこない……」
そんなふうに感じたことはありませんか?
大丈夫。それが正常な感覚です。見えないほど小さな世界ですから。
この記事では、原子や素粒子の質量を扱うときに使う「統一原子質量単位(ダルトン)」について、解説していきます。
基本となる定義や換算値、よく出る粒子の質量、試験での出題パターンまで、必要なポイントをコンパクトに整理して解説します。
放射線技師国家試験で頻出のこの単元を、過去の出題傾向と物理の基本に基づいて、噛み砕いて紹介していきます。
統一原子質量単位とは?
名称から、質量を表す単位であろうことは分かるかと思います。
でも、わざわざ長ったらしい名称にしているってことは、単なる単位ではないんです。
名称に「原子」が付いていることから、原子や原子核といった小さいものの質量を表すときに使うのが「統一原子質量単位:Da(ダルトン)」なのです。
原子や原子核は目に見えないほど小さいですよね。
そんなサイズのものを g や kg で表すのはちょっと分かりにくいだけですよね。
質量を表すには小さすぎる微粒子たち
電子や陽子、中性子といった粒子は、とにかく小さくて軽い。
その質量を kg や g で表そうとすると、なかなか苦労します。
たとえば陽子の質量は 1.6726×10−27 kg……
正直、ゼロが多すぎて直感的にわかりづらいですよね。
10−27 kgって言われても、まったくイメージが湧きませんよね。
小さすぎんねん!

kgやgじゃなく、原子用の専用単位が必要
普通、質量の単位と言えば、[kg] や [g] ですよね?
統一原子質量単位では [kg] や [g] は使いません。
原子・原子核の質量を表すのに、[kg] や [g] では大きすぎてサイズ感がミスマッチです。
そんな超小型の粒子の質量を扱うために考え出されたのが、統一原子質量単位です。
記号は「Da(ダルトン)」と書きます。
これは、化学者ジョン・ドルトンにちなんで名づけられたものです。
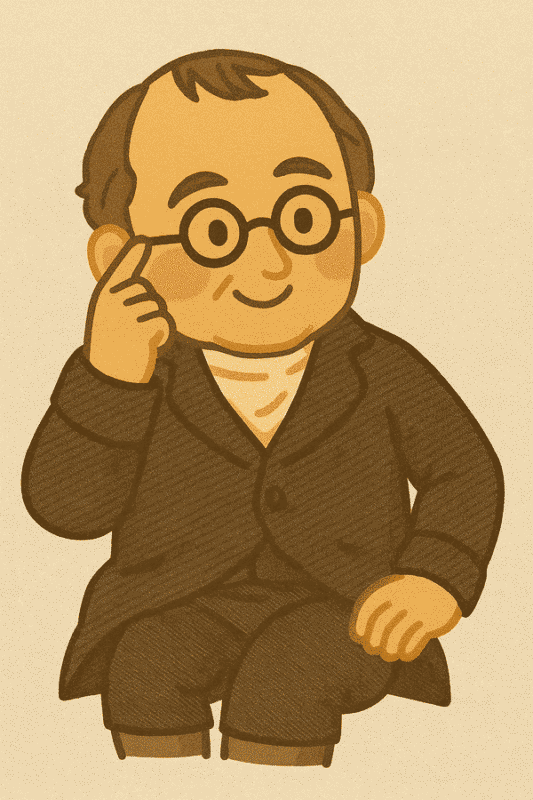
ちなみに、DaはSI併用単位という扱いです。
1Daの定義と意味
別に定義とか知らなくても解ければ良くない?
そんな声も聞こえてきそうですが、「理解」するためには定義は大切ですよ。
しかも、1Da(かつては1u)の定義は国試や主任者でも出題傾向があります。
また定義かいな~。


そんなに難しくないから頑張って。
炭素12の質量を12で割ったもの
「1Daって、どれくらいの重さなの?」という疑問には、こう答えましょう。
炭素12(${}^{12}_{\,\,6}\mathrm{C}$ )原子の質量を12で割ったもの、それが1Da。
つまり、軌道電子を含めた質量数12の炭素原子1個の質量を12等分した質量、ということです。
このように定義することで、微粒子の質量を相対的にわかりやすく比較できるようになりました。
統一原子質量単位の基準は「質量数12の炭素原子の質量」です。
質量数12の炭素原子の質量を 12Da とし、その 1/12 を 1Da としています。
統一原子質量は${}^{12}\mathrm{C}$を基準とした相対的な質量と考えることができますね。
よく出る粒子の質量をDaで整理してみよう
主だったものをあげておきましょう。
| 粒子 | 統一原子質量 |
|---|---|
| 電子 | 0.000548 Da |
| 陽子 | 1.007276 Da |
| 中性子 | 1.008665 Da |
| 重水素 | 2.014102 Da |
| α粒子(${}^{4}\mathrm{He}$) | 4.00260 Da |
| ${}^{12}\mathrm{C}$ | 12 Da |
Da表記なら、kgのように桁数が膨れあがることなく、質量の比較がずっとスムーズです。
桁数多くて、コッチも嫌や


まぁ、そうなんだよね。
1の位だけならいいんだけど、小数第5位くらいまでは計算で使うんだよね。
使いやすいんだか使いにくいんだか分からない。
ってのが正直なところだね。
他の単位との換算方法
1Daの単位換算は核反応や質量欠損の計算問題と併せて登場します。
覚えていれば簡単に対処できますので、ご安心を。
kgに換算すると?
1Da をMKSA単位系の質量に置き換えると 1.6605×10-27 kg です。
国家試験ではこの値が問題文に記載されていることが多いので、暗記の必要はそこまで高くありません。
ただし計算問題で使うことがあるので、 「1Daはすごく小さいkg」 という感覚だけは持っておきましょう。
※主任者試験では1Daが何kgなのかを問うものが出題されます。
1.6605×10-27 kgであることを知らない場合は詰むことになります。
1Daが931.5MeVであることを利用すれば求められますが、計算ですので時間がかかります。
931.5MeVを知らなかったら本当に詰みです。
例)第1種 放射線取扱主任者試験 66回(2021年)問2
エネルギー(MeV)に換算すると?
1Daの質量、これをエネルギーに換算すると 931.5 MeV となります。
私が学生の頃は「暗記必須!」と言われていましたが、最近の出題では問題文に明記されることも増えており、以前ほど覚えなければならないプレッシャーはありません。
この値は「質量欠損」や「核分裂エネルギー」などの計算でよく使われるので、使い方は把握しておきましょう。

試験では932MeVと丸められる場合もあります。
小数点以下がない分、計算が少し楽になりますね。
「u」と「Da」の違いは?
かつては u が使われていましたが、現在は Da が使われています。
過去問などで u が使われているものは、少し古めの問題って解釈できます。
では、中身を見ていきましょう。
記号が変わっただけ。意味はほぼ同じ
昔の参考書や資料では、「u(ユニファイドマスやユニット)」という表記を見かけることがあります。
でも安心してください。1uと1Daは、数値も定義もまったく同じです。単に記号が違うだけです。

厳密には違うんじゃがの。
実用的には変わらんぞい。
2019年から正式に「Da」推奨へ
2019年、国際的に「u」ではなく「Da」を用いることが正式に推奨されました。
国家試験でも「1Da」と表記されることが増えてきていますが、もし「u」が出てきても「Daと同じ」と思えばOKです。
放射線技師の国家試験では Da 表記への移行が完了した感じがしますが、主任者試験ではまだ u 表記を見かけます。
ゆくゆくは Da 表記に変わっていくものと思います。
国家試験でここが狙われる!
登場パターンは決まっています。
水戸黄門で言うと、印籠が出て、「はは~」ってなるようなもの。
ドクターXならば、大門先生の「私、失敗しないので。」のタイミング。
アンパンマンなら、バイキンマンに一度ピンチに追い込まれるようなもの。
もう定番の流れです。パターン化し過ぎて、逆に安心感さえあります。
出題されれば、「はいはい。単位換算とセットね。」と落ち着いて対処しましょう。

わし、水戸黄門大好きなんじゃよ。
ふぉっふぉっふぉ……
たまさん、牛さん。
わしの前に、ひかえおろう──!
電爺、それ……
印籠じゃなくて、「ういろう」ですよね。

んまそう!
オレにも一切れ。


まぁまぁ。
とりあえず、「931.5MeV」は押さえておこうね!
「931.5MeV」は出題頻度が高い
国家試験では、1Daがエネルギー換算で約931.5MeVになるという数値がよく問われます。
これは、質量とエネルギーが E = mc² の関係で結びついているからですね。
選択肢で問われることもあれば、計算問題の中で何気なく登場することもあります。
特に「質量欠損」や「核分裂で得られるエネルギー」を問う問題では、必ずと言っていいほど出てくるので、しっかり押さえておきましょう。

ここは本当に良く出ます。
記憶力がニワトリレベルの私でも、この数字は忘れてませんね。
「質量欠損」単元ともつながる内容
この「931.5MeV」という数値は、単に暗記するのではなく、
- 「質量の減少分がエネルギーに変わった」
- 「1u(1Da)あたり931.5MeV分のエネルギーが出る」
というイメージで理解しておくと、質量欠損 → エネルギー変換の単元にもスムーズに繋がります。
別記事で紹介する【A17:質量欠損を数値で実感しよう ― 重水素・He・Cで計算練習】や【D20 核反応】(執筆予定)とも非常に関係が深いので、合わせて確認しておきたいところです。
実際に出題された国試問題を見てみよう
ちょっと古いですけど、2004年に実施された第56回からの出題をご紹介しましょう。
第56回 2004年 問39
原子質量単位(MeV)はどれか。
- 931.5
- 511
- 12.4
- 6.63
- 0.511
いかがでしょうか?
解答を確認する。
答えは 1 です。
かなり古いものですが、あっさり選べる問題ですね。
もはや、説明不要でしょう・・・
このくらいの難易度の出題があっても良いですよね。
最近の国試、ちょっと難しすぎない?と思う今日この頃です。
統一原子質量は「質量欠損」や「核反応のQ値」を求める問題としてよく登場します。
そちらはそれぞれ別の記事で細かく解説するとしましょう。
医療現場でこの知識がどう役立つの?
質量がわかると、エネルギーがわかる
放射線治療やPET検査など、医療現場で扱う放射線は、しばしば原子レベルの「質量」や「エネルギー」がカギになります。
ここで重要になるのが今回のテーマ「ダルトン(Da)」や「MeV」などの単位です。
質量をエネルギーに換算できる公式
E = mc²
この公式により、わずかな質量の変化でも莫大なエネルギーが得られることが知られています。
これはPETでの陽電子放出や、放射線治療の核反応にも関わっています。
質量欠損の概念にもつながる
試験では、原子核の質量がバラバラの陽子・中性子の合計より小さくなるという「質量欠損」の考え方が登場します。
このときも、質量の単位として「ダルトン」を使い、差分からエネルギーを計算するのが基本です。
つまりこの知識は、臨床での核反応の理解や、治療線量の設計にも密接に関わっているのです。
漫言放語(まんげんほうご)
オレなぁ、最近ちょっと思ててんけど……
「ダルトン」ってプロレスラーの名前ちゃうんか?

違いますよ! 微粒子の質量を表す単位です!


炭素12元素の質量を12で割った値。
それが1ダルトン。
微粒子?
ほな、オレの体重もダルトンで言うたら、
軽く見えるんちゃうか?

いや、ゼロの数がメッチャ多くなるだけですよ。


むしろ重く見えるな……
先生にだけは言われたないわっ!

まとめ
統一原子質量単位(ダルトン)は、原子や分子などのように非常に小さな粒子の質量を扱うための基準です。
基準には炭素12の質量が使われており、「1ダルトン=炭素12の質量の12分の1」と定義されています。
この単位はキログラムでは大きすぎる場面で活躍し、粒子の質量比較やエネルギー換算(MeV)にも利用されます。
原子スケールの話をするときは欠かせない、大事な基本単位のひとつです。

統一原子質量単位は、原子サイズのものさしみたいなもんなんです。
お願い
本サイトに掲載されている図やイラストの著作権は管理人にあります。
無断掲載や転載はお断りさせていただきます。
また、リンクフリーではありますが、画像などへの直リンクはお控えください。
次に読むならコレ!電爺的おすすめ内部リンク

わしが選んだ、「このページとつながる重要な記事」を紹介しよう。
復習や先取りに使うと、放射線物理の理解がさらに深まるぞい!
他にも気になる記事があったら、検索窓に「A11」みたいな番号を入れて探すのがおススメじゃぞ。
もっと知りたい方へ!たまのすけおすすめ外部リンク

ここまで読んできた皆さんなら、もう一歩踏み込んだ知識に触れてみたくなるはずです。そんな方におすすめの外部リンクを紹介しますね。
Wikipedia|統一原子質量単位
→ 定義・由来・換算値・Daとuの関係など、基本から最新の情報がコンパクトにまとまっています。
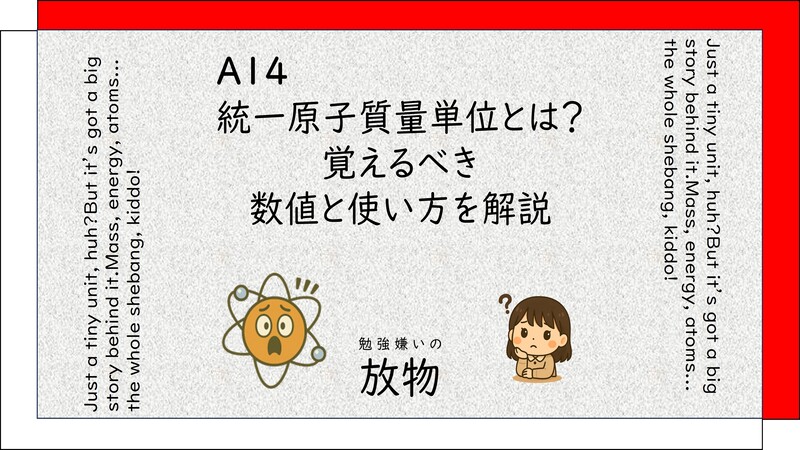

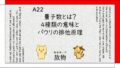
コメント