「複数の粒子がくっつくと、なぜか質量が減っている」
教科書でそんな記述を読んで、なんで?ってなったことはありませんか?
「え? 合体したのに質量が減るって、どういうこと?」と思った方も多いはずです。
この記事では、「なぜ原子核が結合すると軽くなるのか?」という疑問に、お答えしていきます。
鍵となるのは「質量欠損」という現象と、そこから生まれる「結合エネルギー」。
重さが消えるのではなく、エネルギーとして姿を変える――そんな現象が起きているんです。
高校物理では扱わないこの不思議な現象、放射線技師として働くうえで必要な「原子核レベルの現象理解」においてはとても重要です。
それでは、見ていきましょう。
原子核が「軽くなる」ってどういうこと?
原子核を作るとき、どうして質量がちょっと減るのでしょうか?
「軽くなる」って、一体どういうことなのかを見ていきましょう。
「結合」したはずなのに、なぜ質量が減る?
バラバラの陽子や中性子を集めて原子核を作ると、本来はその合計が「全部足しただけの質量」になるはずですよね。
ところが、実際にできた原子核の質量を測ると、なぜかちょっとだけ軽くなっているんです。
たとえばヘリウムの原子核は、陽子2個と中性子2個で構成されています。
でもそれぞれを単体で測った質量を足し合わせたより、できあがったヘリウム原子核は少しだけ質量が少ないんです。
この「どこかへ行ってしまった質量」が、次のカギになります。
オレの体重が100kgやろ。
たなまる先生の体重を120kgとして考えると・・・


ちょっと待てぃ!
なんで私の方が重い設定なんだ?
85kgにしといて~。
本来ならお二人の合計は・・・
100kg+85kgで185kgにならないといけない。
でもなぜか185kgよりも軽くなっちゃうってことですね?


そう!
例えば、合計が180kgだった場合は、5kgはどこ行った?ってことになる。
その理由を見ていこう。
質量が減る=エネルギーに変わっている!
「質量が減るなんておかしい」と思うかもしれませんが、安心してください。
消えたわけではなく、エネルギーに変わって放出されていたんです。
原子核ができるとき、「安定した状態」になるためにエネルギーを放出します。
この放出されたエネルギーのぶんだけ、質量が軽くなる。
これがまさにアインシュタインの有名な「質量とエネルギーの等価性(E = mc²)」という考え方なんです。
「エネルギーに変わって放出されていた」とは言いましたが、エネルギーがどっかに飛んで行ってしまったわけではありません。
それぞれの粒子の軽くなってしまった質量を使って、粒子同士が結合しているんです。
図で見てみると分かりやすいかもしれません。


こんな感じでしょうか。
イメージはできましたか?
この現象を「質量欠損」と呼ぶ
このように、原子核ができるときに失われたように見える質量のことを「質量欠損」といいます。
国家試験に頻繁に登場する文言としては
「原子の質量はそれを構成するそれぞれの粒子の質量の総和より小さい」
というものがあります。
質量欠損を説明する重要な文言ですから、覚えておいてくださいね。
すべての安定な原子核に共通する現象で、安定な核ほど質量欠損は大きいのが特徴です。
つまり、「どれだけのエネルギーを放出して安定になったか」を、この質量の差で表しているんですね。
減った質量はどこへ?正体は「結合エネルギー」!
原子核ができるときに減った質量が、どんなエネルギーに変わったのか?
その正体を「結合エネルギー」という視点から見ていきましょう。
結合エネルギーは「核をバラバラにするのに必要な力」
原子核ができるとき、粒子が結合して「質量が減る」現象が起きます。
このとき減った質量は、エネルギーに変わって放出されています。
この質量欠損をエネルギーに換算したものを結合エネルギーと呼びます。
では、結合エネルギーとは何か?
それは一言で言えば、原子核をバラバラにするために必要なエネルギーです。
たとえば、できあがった原子核をもう一度、バラバラの陽子や中性子に戻そうとするとき。このときは外からエネルギーを与えないといけません。なぜなら、強い力で引きつけ合っている核子同士を引き離すには、かなりのエネルギーが必要だからです。
つまり、原子核の中に閉じ込められているエネルギーを「引きはがす」ためには、そのぶんの結合エネルギーと同じだけの力をかける必要がある、ということなんですね。
質量欠損をエネルギーに換算する式:ΔMc²

原子核は、陽子や中性子が集まってできています。
でも、これらをすべて足し算した質量と、実際の原子核の質量を比べると……あれ? ちょっと軽い?
この「消えた質量」のことが 、質量欠損 でしたね。
でも、この質量、どこかに消えてしまったわけではありません。
これを国試によく出る文言で示すと
「原子の質量はそれを構成するそれぞれの粒子の質量の総和より小さい。」
という表現になります。この文言を見かけたら、
「あっ!質量欠損のことを言っているな!」
と思わなければなりません。
アインシュタインの有名な式 E = mc² によれば、質量はエネルギーに変わる のです。
バラバラのときの質量の合計からくっついたときの質量を引くと、どれだけ軽くなったかが分かりますよね。
その軽くなった分をエネルギーに換算していきます。
$$
\color{#B22222}{
\pmb{
\begin{aligned}
E&=⊿mc^2\\
&=(バラバラのときの質量の合計-くっついたときの質量)c^2
\end{aligned}
}}$$
つまり、原子核ができるときに発生する「質量の減り」は、「結合エネルギー」として放出されていたのです。
この 結合エネルギー は、原子核をしっかりまとめる“のり”のような存在。
原子核をバラバラにするには、このエネルギーと同じぶんの力を外から与えないといけません。
結合エネルギーのグラフが教えてくれること
核子たちは、お互いに「中間子」という粒子をやり取りしながら強く引き合っています。
このやり取りによって、原子核はひとつのまとまりとして存在できているのです。
この「中間子のやり取り」こそが、核子同士を結びつける強い力=結合エネルギーの正体なんですね。
詳しくはA18:核力ってなに?荷電独立性までやさしく解説でお話ししましょう。
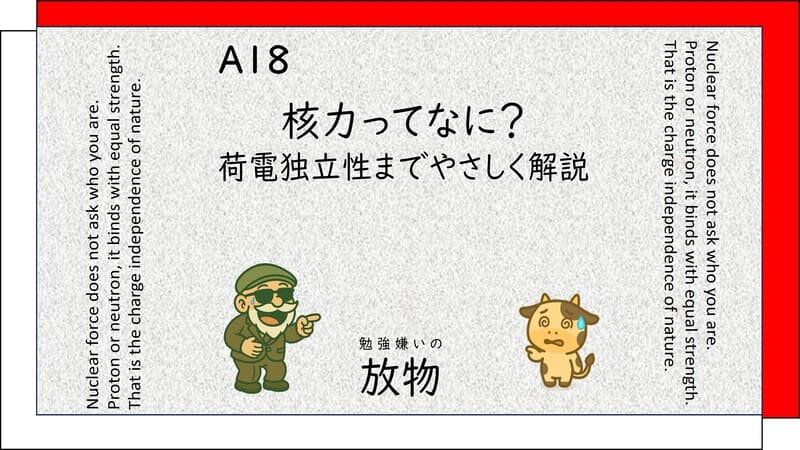
核子1個あたりの結合エネルギーとは?
結合エネルギーとは、原子核を構成する陽子や中性子(これらをまとめて「核子」と呼ぶんでしたよね。)をバラバラにするのに必要なエネルギーです。
つまり、原子核がどれだけしっかりまとまっているかを示す目安になります。
ところが、原子核は元素によって大きさが違います。
小さなヘリウム核と、大きなウラン核では、核子の数も結合エネルギーの合計も当然異なります。
そこで便利なのが、「核子1個あたりの結合エネルギー」という指標です。
これは、原子核全体の結合エネルギーを、中に含まれる核子の数で割ったもの。
こうすることで、大きさの違う原子核同士でも、どれだけ「しっかりまとまっているか(安定しているか)」を公平に比較できるようになるのです。
アメ玉を1粒買うか、100個入りの大袋で買うかで単価が違うってのに似てるな。


えっ!
牛助が本質をついた例えをしてる。
まさにその通りなんだよ。
その単価を比較することで原子核の安定度を見ているんだ。
この「1個あたり」に換算する考え方が、グラフを正しく読み解く鍵になります。
核子1個あたりの結合エネルギーを数値化してみる
原子核の結合エネルギーの合計値を核子の数で除したものです。
これがそこそこ国家試験に出るのです。
核子1個あたりの結合エネルギーは56Feが最も高くなり 8.8MeV にもなります。
質量数12以降の平均値は 8.0MeV です。
質量数12以前は変化が大きいので平均値の算出からは除外されています。
なぜ56Feで最大値になるのか。
疑問に思った方はいませんか?
こういうところに疑問を持つか、聞き流すかで理解度に差が生まれると思っています。
質量数56までは、核子が増えるごとに結合エネルギーが優位に増加していきます。
質量数56以降は事情が変わります。
結合エネルギー自体は増加するのですが、同時にあるものも増えていきます。
それは・・・
陽子同士のクーロン斥力です。
くっつこうとする結合エネルギーの増加に対して、離れようとするクーロン斥力の増加の方が多くなってしまうのです。

したがって核子1個あたりの結合エネルギーが低下してしまいます。
「鉄」あたりがいちばん安定な理由

結合エネルギーのグラフを見ると、鉄(Fe)やニッケル(Ni)あたりの原子核が、核子1個あたりの結合エネルギーが最大となっています。
これはつまり、それ以上強くは結びつけられないほど、がっちりまとまっているということです。
なぜこのあたりが最も安定するのか。
それは、静電気による斥力(陽子同士が反発し合う力)と、強い核力(核子同士を引きつける力)とのバランスが最もよく取れているからです。
陽子が少なすぎると引きつけ合う力が弱く、陽子が多すぎると反発し合う力が大きくなり、どちらも不安定になります。
そのちょうどよいバランス点が、鉄やニッケルあたりの中くらいの原子核なのです。
バランスが大事なんですね。

このグラフが示す、核分裂と核融合の本質
先ほどのグラフ(核子1個あたりの結合エネルギー vs 質量数)を見ると、山のようなカーブを描いて「鉄(質量数56あたり)」でピークを迎えていることが分かります。
そしてこの形こそが、核融合と核分裂の両方でエネルギーが取り出せる理由を視覚的に示してくれています。
たとえば、鉄より左側(=軽い元素)のあたりを見ると、1個あたりの結合エネルギーはまだまだ低め。
この領域の原子核どうしがくっついて、より重い原子核になる(=核融合)と、結合エネルギーが増えます。
つまり、「結びつきが強くなる」=「安定する」ことを意味し、その差分がエネルギーとして放出されるわけです。
逆に、鉄より右側(=重い元素)では、核子1個あたりの結合エネルギーが少しずつ下がっています。
この領域の重い原子核がバラバラに割れて、より軽い原子核に分かれる(=核分裂)と、やはり結合エネルギーが増えます。
つまりこちらも「安定する方向」への変化となり、差分のエネルギーが放出されるのです。
要するに、このグラフの両端から「鉄のあたり」へ向かって変化すればするほど、エネルギーが出るという構造になっているんです。
これが、核融合(軽い原子がくっつく)でも、核分裂(重い原子が割れる)でも、
どちらでもエネルギーを取り出せるという仕組みの「本質」なんです。
いずれオレが食肉になるときもエネルギーが放出されるんかな~?


牛助、なにげにブランド牛(松阪牛)だからな。
たっぷり出そうな気がするよ・・・
私もだけど。
実際の問題を見ていきましょう。
第68回 2016年 PM70
核子1個当たりの平均結合エネルギーが最も大きいのはどれか。
- ${}^{4}\mathrm{He}$
- ${}^{12}\mathrm{C}$
- ${}^{24}\mathrm{Mg}$
- ${}^{56}\mathrm{Fe}$
- ${}^{226}\mathrm{Ra}$
いかがでしょうか?
解答を確認する。
答えは 4 です。
核子1個あたりの結合エネルギーは56Feで最大になります。
医療現場での関わり
医療現場で「質量欠損そのもの」を直接意識する場面はあまりありませんが、実は放射線に関わるいろいろな現象の根っこにこの考え方が関係しています。
核医学検査の場合(RIの壊変)
たとえば、PET検査で使われる ${}^{18}\mathrm{F}$ や、骨シンチで使われる ${}^{99m}\mathrm{Tc}$ といった放射性同位元素(RI)は、壊変することで放射線を出します。
このときに放出されるエネルギー(γ線やβ線など)は、壊変前後の質量の差――つまり質量欠損から生じたエネルギーです。
だから、壊変で出てくる放射線の「量」や「強さ」には、実は質量の変化が関わっているんですね。
放射線治療の場合(粒子線と核反応)
陽子線治療や重粒子線治療のように、加速した粒子を体内に打ち込む治療では、体内の原子核との核反応が起こることがあります。
このときにも、反応の前後で質量にわずかな違いが生じ、その分のエネルギーが放出されることがあります。
これも、広い意味で言えば「質量欠損」が関係している現象です。
まとめ
原子核ができるときに失われた質量(質量欠損)は、けっしてどこかに消えたわけではなく、エネルギーに変わって放出されていたのです。
このエネルギーこそが「結合エネルギー」であり、原子核をしっかりつなぎとめている大切な力でもあります。
ふだんの生活ではなかなか意識しない現象ですが、放射線を扱う医療分野においても、核反応の背景にあるこの仕組みを理解しておくことはとても重要です。

このように、見えないところで質量の差(質量欠損)がエネルギーになっているんです。
病院では感じにくい部分ですが、放射線を使っている以上、切っても切れない関係なんですね。
次に読むならコレ!電爺的おすすめ内部リンク

ほれ、ここまで読んだんなら、次はこのあたりを見ておくとえぇぞい。
もっと知りたい方へ!たまのすけおすすめ外部リンク

ここまで読んできた皆さんなら、もう一歩踏み込んだ知識に触れてみたくなるはずです。そんな方におすすめの外部リンクを紹介しますね。
核融合の先生
https://jpscience.info/mass-deficiency/?utm_source=chatgpt.com
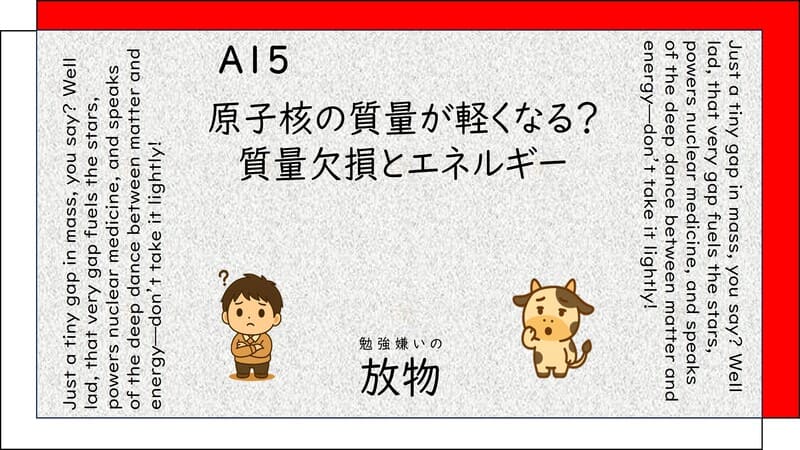


コメント